国学院大学法学部横山実ゼミ
Martin Wrightの「修復司法」の理念(2)
(この随筆は、中央大学犯罪科学研究会の機関誌から転載しました。)
横 山 実
2つのケースを紹介した上で、ライトさんは、修復司法の原理を考察している。以下、彼の考察の要点を紹介しながら、修復司法の日本への導入について考えてみたい。

犯罪行為は、しばしば、個々の被害者を害しているので、社会の最初の反応は、被害を回復するよう試みるべきである。英国では、この働きの主たる担い手が、民間の団体であるVictim Supportである。Victim Supportは、イギリス、ウエールズ、北アイルランドの370の地方組織を有しており、そこでは、800人のスタッフと、4,000人の委員会メンバー、12,000人の訓練を受けたボランティアが働いている。日本では、ここ数年、犯罪被害者救済の必要性が認識されるようになり、東京医科歯科大学や常磐大学の研究者などが、犯罪被害者のために、相談を受けるようになっている。しかし、英国のように、全国において組織的に救済活動を展開するに至っていない。最近では、警察が、犯罪被害者活動に力を入れつつある。被害者救済は、心的外傷からの救済といった精神的ものから、経済的な救済まで、多方面にわたる。つまり、警察の管轄外の活動を含むことになるので、Victim Supportのような、それら多方面における被害者救済活動を統括する組織が、必要となろう。
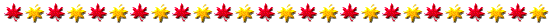
次に、もし加害者が発見されたならば、その者の償いが求められる。償いは、金銭的なものに限らない。日本では、しばしば、示談という形で、金銭的な償いが行われている。しかし、その多くは、被害者への謝罪の外形を整え、検察官に起訴猶予処分にしてもらったり、裁判で科刑を軽くしてもらうためである。そのために、裕福な加害者に依頼された弁護士は、被害者に示談金を押しつけ、強引に示談の形を整えることがあるという。
償いは、被害者本人に対するものである場合と、社会に対する場合とがある。ペータのケースでは、当初、被害者のための掃除の仕事が、話し合われた。最終的には、ペータは、それとともに、地域社会に貢献する奉仕的な仕事をすることに同意したのである。被害者に直接償う例としては、侵入盗をした者に、(監視の下で)扉の鍵を取り付けさせたり、窓を修理させたりすることが、挙げられている。
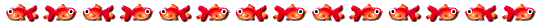
一般には、地域における奉仕的な活動は、仲裁人が被害者の意思を確認したとき、被害者が自分のために償いをすることを断る場合に行われる。その活動の例としては、身体障害児が水泳するのを助ける、学習困難児に本を読んであげる、車椅子使用者を店に連れて行く、老人の昼食クラブの運営を助けるということが挙げられている。
加害者達は、しばしば、自分たちが社会的に恵まれていないと、疎外感を持つている。彼らにとって、自分たち以外にも、恵まれていない人がいることを認識すること、また、その恵まれていない人に、何か建設的なことができるのを見いだすことは、自分たちの疎外感を克服するのに有意義なことである。日本でも、少年院で処遇を受けている少年には、仮退院の前に、老人ホームで老人の介護をしたり、地域の公園で掃除をしたりしている。特に非行少年の場合、社会的奉仕は、その少年にとって、貴重な体験となるであろう。ただし、老人や身体障害者の介護といった仕事は、嫌々ながらやるのでは、心の通った介護にならず、かえって、介護の対象者に迷惑を掛けることになりかねない。社会的奉仕活動の対象者への配慮が、必要であろう。
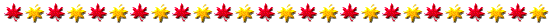
リリアンさんの場合のように、被害者の多くは、自分に直接償うことを望んでいない。その代わりに、本当に詫びているのを、これからの行動で示すように、加害者に求めることがある。例えば、加害者が少年の場合、規則正しく通学すること、トラブルに巻き込んだ友達と交際しないことなどが、求められることがある。また、激情の制御力を養うプログラム、薬物・飲酒・賭事への耽溺を矯正するプログラム、あるいは、職業訓練を受けることが、求められることがある。被害者がこれらの求めに、自分の意志で応じるならば、刑事司法や少年司法において、これらを命じられる以上に、効果が上がることであろう。
以上が、償いをする実践的な方法である。修復司法では、これらの償いによって、加害者が、自分の自己評価を高め、再び犯罪を犯さず、地域社会に再び受け入れられることを、期待しているのである。

アイルランドの人形( Doll in Irland)
修復司法の中核は、加害者に償いをさせることである。そのために、専門スタッフあるいはボランティアが、ソーシャル・ワーカーとして、犯罪の被害者と加害者との仲裁の役割を演じる。ライトさんが強調するように、その過程は、すべて、「随意(voluntary)」でなければならない。「随意」であることは、修復的司法の真髄であり、また、その限界でもある。
仲裁の過程で「随意性」を確保するには、警察、検察および裁判という、刑罰権力を背景とする公的機関より、全英仲裁協会のような民間機関が、仲裁の主導権を取るべきであろう。刑事司法や少年司法で処分を決定する権限を持っている者が、仲裁役を演じると、少なくとも、加害者の方では、仲裁を受け入れなければ、処分が不利になると思い、その仲裁を受け入れることになりかねない。その場合には、仲裁の場で、加害者が心から償いを申し出たり、償いの約束をしたりすることは、期待できないであろう。
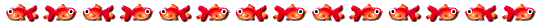
ところで、修復司法の働きを、刑事司法や少年司法からのダイバージョンとしてとらえる立場がある。ダイバージョンと結びつけると、加害者は、刑事司法や少年司法から早く解放されたいために、本当は被害者に会って詫びる意思はないのに、それを装って、仲裁の手続に乗ることが出てくるであろう。その場合は、ライトさんが主張する「随意性」は、確保されないことになる。
ライトさんは、修復司法を、犯罪に対する反応として捉え、刑事司法とは異なるものと考えている。彼によれば、刑事司法は、加害者が生じさせた害と、その加害者に対する一層重い害(刑罰)とのバランスに基づいている。これは、古典学派の刑罰理論に基づく考えで、日本でも原則的に妥当する。修復司法は、その応報刑的考えに反対し、犯行の後に、復旧したり、善を行ったり、癒したりすることを、目的としている。このことにより、家族の結合を強め、地域社会を再構築しようとしているのである。そのような理想から、ライトさんは、この論文の表題に、「刑罰」から「修復」へという副題をつけている。
犯罪を犯した人すべてに、「随意」に償いをさせることは、理想である。その「随意」を引き出すために、仲裁人が重要な役割を演じなければならないことも、首肯できる。しかし、仲裁人がどんなに努力しても、加害者すべてが、「随意」に被害者に会って自分の犯行を悔い、償いを申し出ることはありえないであろう。二つの事例のように、加害者が少年や若者の場合には、彼らに可塑性があるので、修復司法の効果が期待できる。しかし、常習窃盗犯や暴力団関係者が加害者の場合には、「随意性」に基づく修復司法の効果を、期待できないであろう。
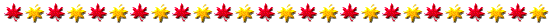
修復司法の働きかけは、一般には、加害者が発見された後、出来るだけ早い時期に行う事が望ましい。それを行うためには、警察が、被害者に加害者を発見した直後に、それを通知する必要がある。日本では、最近になって、やっと警察による通知制度が確立した。これで、仲裁活動の前提の一つが、整備されたことになる。できるだけ早期に仲裁するためには、英国の全英仲裁協会のような仲裁専門機関の設立が、特に望まれることになろう。
ところで、被害者と加害者が、仲裁を「随意」に受け入れることを前提とするならば、仲裁に入るのは、刑事司法や少年司法の手続に乗ってからでも、かまわないことになる。例えば、試験観察に付された少年に対して、家庭裁判所の調査官や、民間の補導委託先が、加害者との仲裁をすることが可能であろう。また、少年院に入所している少年の場合には、保護司が環境調整活動の一環として、被害者と仲裁の労をとることも可能かもしれない。宗教教誨師や篤志面接委員といった人的資源を、仲裁人として活用することも、可能かもしれない。
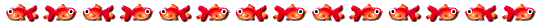
日本では、民間の被害者救済組織が発展して、全英仲裁協会のような全国的なNGO組織を確立することが、すぐに期待できないであろう。そうであれば、非権力的行政の一端を担っている家庭裁判所の調査官や調停委員、保護司、民生委員といった人的資源を活用して、刑事司法や少年司法の過程のどの段階でも、あるいは、その過程の前後でも、被害者と加害者とが仲裁によって会うことを希望するならば、仲裁を行い、修復司法の効果を追求するのが望ましいであろう。
ライトさんが主張するように、全面的に「刑罰から修復へ」向かうのは、無理であるが、それでも、修復司法の理念に基づいて、特に少年や若者である加害者へ働きかけを活発化することは、望ましいであろう。

