開かれた点字の世界の扉
翔太君との関わり合い
国学院大学 柴田保之
はじめに
平成6年9月12日、600gあまりの超未熟児で生まれた翔太君は、保育器の中での生死のたたかいを何とかくぐりぬけ、私たちの世界にやってきた。しかし、保育器の中で手厚い医療を必要とした翔太君は未熟児網膜症による視覚障害を避けることができなかった。
また、周りの人たちが事物に対して払っている関心に自分の関心を重ね合わせることをめぐって、ある特徴をもっており、それがかけがえのない個性を形作ってきた。それは確かに、周りの人にあるわかりにくさを与えることにもなってきたが、また、類まれな集中力を培うとにもつながってきたといえよう。
そんな彼に出会ったのは1997年の暮れのことだ。好奇心旺盛に外界を探索する翔太君を見て、いつか点字を読ませたいと、ひそかに決意した。
それから4年半ほどの関わり合いは、最初に思い描いたような歩みとはずいぶんちがうものだった。しかし、今、小学2年の翔太君は、点字とあまり大きさの変わらない点字型のリベットを触覚的に区別したりするようになり、今まさに点字の世界の入り口の扉をあけようとしている。
ここでは、翔太君の点字の世界への個性的な歩みと、その中で明らかになったことをまとめることにしたい。なお、論述は、私自身の関わる以前の1997年5月のところから始めることとする。
1.玉入れの学習と様々な操作教材(97.5〜)
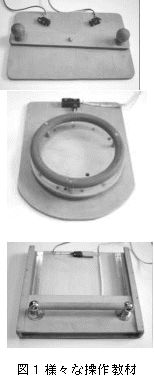 最初の時期に、中心的に関わったのは、ボールを缶や穴に入れる位置づけの学習と、押す、引く、回すなどの様々な方向の調整を伴う操作の学習とである。
最初の時期に、中心的に関わったのは、ボールを缶や穴に入れる位置づけの学習と、押す、引く、回すなどの様々な方向の調整を伴う操作の学習とである。
玉入れの学習では、ビー玉やゴルフボールを缶や穴のあいた箱に入れるということができるようになっていた。手の使い方は、ボールや玉を一方の手に触れると自分でつかみ、いったん誘導することによって缶や箱の存在を知らせれば、物を渡すたびに渡されたものをつかんだ手で缶の口や箱の穴を探し、そこで放すことができた。穴や缶を定位するこの触覚の受容については、つぎのようなことがいえる。
すなわち、翔太君の目的は穴や缶に玉を入れて音を出すことだが、そのために穴や缶を探そうとする。この時の手の出し方は、穴に到達するまで試行錯誤的なものだが、すでに繰り返し行っていたり、提示する側もそれらを一定の位置に置いたりするので、比較的容易に到達できる。そして、いったん到達すればそこへ再び手を伸ばすのは、さらに容易となる。なぜならば、その位置は、到達した時の手の伸ばし具合として、その方向や距離が保持されているからだ。別の言い方をすれば、最初に到達する際の手の受容は、伸ばす際に触れる外界の対象の位置関係に向けられるよりも、手の伸ばし具合、すなわち自らの身体の方に向けられているということになる。だが、これこそ、外界の事物の位置関係を構成する出発点にほかならない。
一方、これとは別の系列の学習として、外界の対象を積極的に操作する学習がある。すなわち、図1に示したような教材での、片手や両手による直線や曲線などの運動である。こうした教材は、運動そのものから生じる運動感覚やバランスの変化などの自己受容性の感覚を駆使して操作されるものであるが、翔太君は、こうした操作を深く集中して何度も何度も繰り返すことが多く、私たちに近寄りがたいような印象を与えた。こんな時いったい、翔太君は何を感じ、何を楽しんでいたのだろうか。
まず、最初にあげられるのは、こうした操作を通して生まれるリズムである。運動も一つのリズムであり、また、操作の結果としてのチャイムの音などもまた一つのリズムである。こうしたリズムを生み出すことが、翔太君の行動の目的の一つなのである。
だが、リズムを生み出すだけならば、同じ運動の反復をすればよい。常同行動や自傷と呼ばれるものはそれにあたる。そこでもう一つの重要な目的として、新しい発見というものがあげられる。そして、この新しい発見には、二つの側面がある。それは、一つは外界に関する発見であり、他方は自分の身体の可能性に関する発見である。ここでは、外界の性質やそこに存在する関係は、運動と不可分であるために、両者はわかちがたく結びついている。したがって、何度も何度も繰り返される運動の中で、外界と身体の両者について、新しい発見やその確かめを行っているといえるのである。その一例として次のものをあげておこう。すなわち、両手のハンドルスイッチで、片手で十分操作したあと、自分から両手を出し、相反する両手の方向の動きを協応させて行い、自分で拍手するという場面があった。まさにその教材の新たな発見であるとともに、自分の身体の可能性の新しい発見がなされていたのである。
2.はめ板の学習の拒否と豊かになっていく言葉(98.5〜)
上のような学習の発展として、形のはめ板の学習(98.5.25)や電池入れ(5.18)の学習に進んだ。これは、点字への歩みとして重要な一歩となるはずの学習であった。そして、ちょうどそれは翔太君が言葉を話し始める時期と重なっており、板が穴に入るときに「パッチン」という声を出して大喜びで入れるようになった。また、「まる」「さんかく」「しかく」という言葉をまねるようにもなった。また「ル」という音を舌でうまく出せず下唇をかんで「ル」の音を出そうとするのがとてもほほえましく見えたりもした。まるを5枚横に並べて入れていく教材では、まるを横にすべらせながら、穴を探していく。この探し方は、以前の玉入れの場合の探し方と比較すると、手の伸ばし具合という身体に関することよりも外界の対象の位置関係に向けられたものということができるだろう。なぜなら、最初の1枚を入れたあと、2枚目からは、前に入れた位置を基準にして、そこから次の穴を探しているからである。
しかし、こうした学習は残念ながらことごとく「おしまい」のひとことで拒否されるようになる。子どもが拒否をするということは子どもの意志の明確な表明なのだから、子どもの自発性を大切にすると言う意味では喜ぶべきことであるが、さすがに、この学習を通過できなければ点字への道は開けないのではとの思いにかられた。しかし、むりじいするわけにもいかず、しばらくは、以前から使ってきたスイッチの教材中心の学習が続くことになった。
ところでこの学習の足踏みの時期に、翔太くんの言葉はどんどん豊かになっていったが、次のような面白いことが起こった(99,3.1)。すなわち、棒に木の短い筒を10個さすようになっている教材で、翔太君の手をとって一つずつ数えながらさす学習をしていると、自分で、次のような行動をし始めた。すなわち、筒を渡すと棒の先端に入れたところで「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」という声を出しながら筒を小刻みに上下に動かし、今度は「すーっ」と言いながら下まですべらせて手を放すと、「おーっ、うまーい。おーっすばらしい。まったくあたらしい」と決まったセリフを言うのである。しかもその時々の手のしぐさも決まっていて、「おーうまーい」のところでは小指で鼻の下をさわった。
これは、学習としては、筒と棒の関係づけや、筒がいっぱいになるまでの一まとまりの長い運動を行うという意味を持ってはいるが、翔太君の喜びという点から見ると、一連のセリフと動作を歌のようにとらえ、そのまとまりを繰り返し喜んでいるということになろう。翔太君にとって、学習は、こうした歌のような一つの流れをもったものでなければ楽しくないということでもあり、その点からしてもはめ板の学習は、つまらなかったということかもしれない。そして、その後も、学習をどのような「セリフ」とともに行うかということが、翔太君にとってその学習が気に入るものであるかどうかの、大変重要なポイントであり、学習に応じて、いろいろな言葉のかけ方を現在にいたるまで行っているということもつけくわえておこう。
そして、2000年4月14日、「犬のおまわりさん」の歌にあわせてはいはいの姿勢で片足を軸にしてぐるぐる回り始めるという大変おもしろいことが起こったのである。これまでしたことのない踊りだとのことだったが、「犬のおまわりさん」を、犬が回るというふうに解して犬のかっこうをしてまわったということなのではないかと私は考えた。私たちは言葉というものを、視覚像と音との結びつきと考えやすいが、彼にとっては、動作と音との結びつきという側面を強く持っており、この場合、おそらくはいはいのかっこうと「犬」、くるくる回る動作と「まわる」という音声との結びつきがどこかで形成されていたのであり、「犬のおまわりさん」という言葉が、新しい動作を生み出したのではなかろうか。そして、この頃、特定の教材と特定の歌の名を結びつけるということも起こっていた。一例をあげると、バランスのスイッチをやる時に、「よぞらのむこう」と言いながらやるなどであるが、これは、誰かが翔太君の体をゆすりながら「夜空ノムコウ」を歌ったときの体の揺れと、バランスのスイッチにおける体の揺れとが類似していることから生まれた結びつきではないかと考えられる。
おそらく、こうした音声と動作の結びつきには、そんなに多くの繰り返しを要してはいなかっただろう。あたかも一度聞いたメロディーを記憶できる人がいるように、翔太君は少ない回数の経験で言葉と動作の結びつきを作ったのだろう。そして、これは、人間の記憶というものの本質の一端を示したもので、このような力が言語獲得の背景にはあるのだろう。
また、こうしたことに先立って、「これは、スイッチ」(98.11.23)と言って、「スイッチ部」をたたくようにしたり、教材をさわって「ハンドルのスイッチ」(98.12.22)「シーソースイッチ」(99.1.18)のような言い方も生まれていたが、これもこうした動作と言葉の結びつきの一部であったと言ってよいだろう。
 なお、こうしたことと並行して、日常生活の中で数唱ができ始めたので、パソコンで、スイッチを押すたびに一つずつ1から10までの数唱を唱えるプログラムを提示した(99.10.22)。翔太君はたいへんこの教材を喜び、20までの数唱(00.1.28)、50までの数唱(00.5.26)へと発展していった。これは、数唱が一続きの歌のようにして覚えられたものを、スイッチを押す運動によって分節化することにつながった。そして、タイルをスライドさせながら数えるような教材へと発展させていった(00.5.26)が、翔太君の注意は、自らの運動の方に中心的に向けられており、対象の方にはなかなか向けられないため、順序数としての数への発展も困難であり、また基数としての捕らえ方に結びつけるのは、いっそうむずかしかった。しかし、その後もずっと困難なままである。しかし、6点の木のリベットさしにおいて、リベットを数えながら順番にさすようにすると、その位置については、数唱と対応するような運動は見られるようになった。
なお、こうしたことと並行して、日常生活の中で数唱ができ始めたので、パソコンで、スイッチを押すたびに一つずつ1から10までの数唱を唱えるプログラムを提示した(99.10.22)。翔太君はたいへんこの教材を喜び、20までの数唱(00.1.28)、50までの数唱(00.5.26)へと発展していった。これは、数唱が一続きの歌のようにして覚えられたものを、スイッチを押す運動によって分節化することにつながった。そして、タイルをスライドさせながら数えるような教材へと発展させていった(00.5.26)が、翔太君の注意は、自らの運動の方に中心的に向けられており、対象の方にはなかなか向けられないため、順序数としての数への発展も困難であり、また基数としての捕らえ方に結びつけるのは、いっそうむずかしかった。しかし、その後もずっと困難なままである。しかし、6点の木のリベットさしにおいて、リベットを数えながら順番にさすようにすると、その位置については、数唱と対応するような運動は見られるようになった。
 3.複数の位置の関係の構成と、音を空間上に配列すること(00.3.17〜)
3.複数の位置の関係の構成と、音を空間上に配列すること(00.3.17〜)
形の学習から点字の学習へむかう道がいったん断たれてからの経過を述べてきたが、再び点字の学習に向かうために、まず、図のようなリベットの点字を押すと音声が発生する装置の取り組みを開始した(00.3.17)。これは、市販されている50音のひらがなボードの玩具を改造したものであるが、翔太君は、家庭でこの玩具で遊んでおり、順番にさわったり探したりすることが少しずつ出来始めていたため、これをもっと点字につながるものとして、発展させていこうと考えたのである。
だが、これは、学習の順序から言えばいくつもの先立つべき学習を飛ばしたことになる。まだ、同じと違うの関係を処理する見本合わせと呼ばれるスタイルの学習も位置の弁別学習や構成の学習なども取り組んでいなかったのである。しかし、私の思い描いた学習の順序通りに進んでいなくても、翔太君の中で育っている力というものがあるのだから、いろいろな挑戦をしながら考えていけばいいのではないかと考えたのである。
この教材は、家庭で使っていた玩具と全く同じ音声であったこともあって、すぐに、喜んでスイッチを押し始めた。音声は、「ア行」の5文字を入れる場合と、「ア」(1の点)と「メ」(123456の点)というもっとも対照的な2文字を入れるものとを中心に行った。この教材の最終の目的は、指先のリベットの触覚からリベットの位置関係を読み取って音声と結びつけることにあるわけだが、もちろん、最初から、しかもこの教材だけでそのことをめざすには無理がある。そこで、ア行の配列では位置と音声との対応、「ア」と「メ」では、リベットの数の違いから生まれる触覚的な質感のちがいと音声との対応とをめざすことにした。
位置との対応は、すぐに理解され、つぎのような大変面白いことも起こった。すなわち、「ア」と「メ」の学習では、触覚的な質感の違いをきわだたせようと、位置を入れ替えて提示したところ、スイッチの台全体を回転させて、「ア」と「メ」の位置をもとに戻そうとし、私たちがスイッチの台を押さえても、決してゆずろうとしなかったのである(00.5.12)。これは、翔太君がすでに音声と位置との対応がきちんとできあがっているということと、左右の位置関係が回転によって逆転するということも理解しているということを意味していた。しかも、翔太君にとって、物の配列というのは、それを変えられることが許しがたいぐらいに強い意味をもって存在しているということも明らかになった。そして、さらに敷衍すれば、生活の中で空間的基準が翔太君の存在を確定する上で、大切なものとなっているのではないかということがうかがえた。
また、こうした音声の順序という時間的な構造を空間的な配列の順序関係に置き換えるということが、翔太君にとってほとんど抵抗なく理解されていくことは、ピアノなどの鍵盤楽器を操ることと深く結びついていることも、うかがえた。鍵盤楽器についての詳細は省略せざるをえないが、翔太君は、音の高低という本来空間とは無関係なものを、この頃には、鍵盤の左右の配列の関係に置き換えていたのである。
さらに、学習が進むにつれ、単音節を探すだけではなく、「アウ」「イオ」「アメ」「メア」などから、さらに複雑な「アイオ」「メメア」などを、こちらの音声に応じて探すことができるようになっていった。こうした学習の発展はまったく当初予定していなかったものだが、音節やその分解、構成の意識を結果的には高めることにつながり、また、それぞれの位置への音声のわりあても、非常に正確になっていったと言える。
ただし、こうした方向へと学習が進んだのは、スイッチの位置と音声の関係はとらえられるものの、スイッチの表面のリベットの触覚的な質感などと音声との関係には、翔太君の関心が向かっていかないということでもあった。
そのような中で、「ア」と「メ」の状態でスイッチのリベットの表面を指先でさわっただけで、まだスイッチを押していない時に、「これはなんですか」と聞くと「ア」とか「メ」とか答えが返ってくるようになった(01.7.20)。まだ、答えはあいまいだが、この時点では、翔太君の関心が、スイッチの位置から触覚的な質感へと移っており、この時は、「ア」と「メ」とを入れ替えても、抵抗はなかった。
なお、こうしたことと平行して取り組んだものの一つが、2×3の6点の木のリベットさしである。この教材は点字の発声装置以前だが(00.12.3)だが、最初は、抜き取るだけで、自分からさすことはしなかった。それが、「グサッ」という声をかけてあげるとさすようになった(01.5.26)。この学習が、点字の音声発声装置のリベットの配列とどのように結びつけてゆくかということは、現在も課題である。
また、この時期に東京女子大の二人の学生が卒論のために翔太君の家庭訪問をして、木のリベットさしやあいうえおの玩具、紐に通した玉を数えるなどに取り組み、音声の空間化や木のリベットにおける6つの点の位置の理解などが豊かになっていったということもつけくわえておきたい。
4.点字の枠組みの中における点の配列の異同へ(01.9.14〜)
どこかで同じー違うという異同の関係が納得されないかぎり、点字への発展はありえないということはわかっていながらも、その突破口は見当たらない中で、点字の音声発声装置を使って同じ―違うの関係の学習を試みることにした。そして、何度かあっさり拒否されていたものの、少しずつ受け入れられるようになっていった(01.9.14)。これは、点字の音声発声装置のスイッチと同じ大きさの点字のリベットを見本として、これを触らせて、スイッチのどれと同じかということを尋ねるものだが、翔太君にとっては、当然いったい何を聞かれているのかということそのものが理解されない。しかし、「これはなにかな」「同じのはどれかな」というような言葉をかけていくと、見本をよく触ってから、スイッチを押すようになっていった。なお、選択項としては、「ア」と「メ」の2選択、「アイウエオ」の5選択とで行った。
そして、幸いなことに、翔太君は、課題の意味が十分に理解される以前に、この見本との異同を尋ねる一連の流れが気に入ったようで、点字の音声発声装置を出すと、自分から見本がいつも出されるあたりに手を伸ばしてくるようになった。
そして、関心をリベットの方に向けるために、様々な働きかけを工夫した。例えば、これは、「アですかメですか」と聞いてから「1だからア」、「1、2、3、4、5、6だからメ」と言ったりする働きかけである。まるで暗記のための反復学習のようにさえ見えるこうした働きかけだが、これは、あくまで、翔太君の関心をリベットに向けるきっかけを作るためであである。何か決まった音声が伴うことを大変喜ぶ翔太君に発する言葉として苦肉の策でもあった。
ここで、非常に興味深いのは、こうしたやりとりの中で翔太君はスイッチを押し、声が出るととても喜んでいるのだが、そうしたことに関する翔太君の関心とは別のところで、リベットを触るというプロセスが静かに進行しているように見えることだった。翔太君にとって、大喜びにつながるものは、スイッチを押すタイミングやそれに伴う自分や大人の声などなのだが、例えば、見本の「ア」を触った後、選択項にあたる「アイメ」のスイッチを触る時、リベットの表面をなでるようにして、見本と同じ触覚的質感を探り当てる場面が見られたのである(02.3.1)。このことは、すでに翔太君の中にこうした触覚的な弁別の基礎ができあがっていることを意味している。ただ、そこを私と翔太君の共通の関心事として浮かび上がらせる工夫がまだ十分ではないため、その翔太君の行動を学習の中で確実なものとすることができていない。だが、もうあと一歩である。
最近、同じのはどれかというのをやりながら、ア行のそれぞれの点字の番号を言ったところ、翔太君は、自分から覚えて言い始めた(02.5.10)。特に好きなのが、「エは124の点」である。この音声の世界を正確に触覚の世界に結びつけていくことが今まさに求められているところだ。
おわりに
翔太君にとって点字の世界の扉は開かれたとはいえ、その世界の中に足を踏み入れて前進していくのはこれからである。
翔太君との関わり合いの中で学んだことは、まず、果敢に挑み続けていくことの大切さだ。翔太君は、自分の思いに添わないものには決してつきあってはくれない。だからといって、すでに気に入っているものにだけ頼り続けているだけでは、前には進んでいけないし、また、本当の翔太君の力にも出会うことができない。はねかえされることは承知で新しい物をどんどんとぶつけていかなければならないのである。
翔太君にとって一度しかない幼児期を私たちは私たちのやり方で関わった。教育とは、その人の可能性を切り拓く仕事であると同時にその人の可能性を限定してしまう仕事であるということをつくづく思う。もっとやり方を工夫しさえすればオーソドックスな道をたどれたかもしれなかった。私たちは、翔太君をひきつけようとするあまり、ふざけすぎ、学習がいつも騒がしすぎたかもしれない。
しかし、前に進む以外に、どこにも道はない。点字を読み書きし、数を操作する翔太君の姿を夢みつつ、一度しかない翔太君の少年期に向かい合い続けたい。