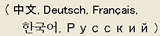| ホーム >> COEプログラム事業の遂行と成果について >> a. 調査 >> グループ1「基層文化としての神道・日本文化の研究」 大韓民国における多鈕鏡調査―扶餘博物館所蔵資料― | |||
| |||
| 調査名:大韓民国における多鈕鏡調査―扶餘博物館所蔵資料― グループⅠ 基層文化としての神道・日本文化の研究 1.調査地 韓国 ソウル・公州郡・扶餘郡 遺物調査地 国立扶餘博物館 踏査地 忠清南道公州郡丹芝里遺跡 忠清南道公州郡宋山里古墳群・武寧王陵 忠清南道公州郡公山城 忠清南道扶餘郡松菊里遺跡 忠清南道扶餘郡陵山里古墳群 忠清南道扶餘郡九鳳里遺跡 忠清南道扶餘郡合松里遺跡 忠清南道扶餘郡軍守里廃寺 2.調査参加者 杉山林継(國學院大學教授・事業推進担当者) 村松洋介(國學院大學大学院博士課程後期) 野内智一郎(國學院大學大学院博士課程前期) 3.調査日程 平成16年8月21日〜平成16年8月24日 4.目的と成果 本調査は、多鈕細文鏡と粗文鏡の細部観察・写真撮影を行ない、出土地や周辺の遺跡に赴き、歴史的背景と地理的背景、さらには鏡を中心とした様々な集団関係を考察することを目的とする。多鈕鏡とその信仰は稲作文化の伝来とも関連し、神道の成立を考証するうえでも重要である。 多鈕鏡の観察・写真撮影は國立扶餘博物館で行ない、同館所蔵の九鳳里遺跡、東西里遺跡、合松里遺跡出土鏡を対象とした。多鈕鏡を使用痕跡・鋳造痕跡・調整部位といった細部にわたって観察することにより、前年度に調査を行なった日本列島出土の多鈕細文鏡と比較して、製作・調整方法や使用時の痕跡といった点で多くの新たな知見が得られた。今後の検討により両者の細部比較から、多鈕細文鏡の製作動向や使用状況などを東アジア的視点で復元し報告する予定である。 写真撮影については、デジタルカメラD1Xのみでの撮影とした。調査対象の多鈕鏡はいずれも貴重な文化財であり、その取り扱いには細心の注意を払った。これらの作業により細部の状況が不明であった多鈕鏡の詳細な画像データを得ることができ、今後の細部検討が容易となった。 多鈕細文鏡を用いた祭祀に副葬・埋納の両者が存在することは周知の事実である。遺跡の踏査においては、その祭祀が行なわれた場を実見し、それを周辺の同時期の遺跡や日本の状況と比較することを目的として、多鈕鏡の出土した九鳳里遺跡、合松里遺跡の現地調査を実施し、日本における多鈕細文鏡出土遺跡の立地状況との比較を行なった。今回踏査した多鈕鏡出土遺跡は、いずれも出土状況が明確ではなく、遺構の性格が不明であるものの、いずれも平野を見下ろす丘陵の中腹に位置するという立地状況であることが指摘できる。さらに日本の古墳文化と深いかかわりのある丹芝里遺跡、公山城、宋山里古墳群(武寧王陵を含む)、陵山里古墳群等の踏査を行なった。 なお、調査最終日には国立中央博物館長の李健茂氏を訪問し、同館所蔵鏡の調査や今後の韓国国内での多鈕鏡調査への協力についてお願いし、快諾を得た。これは来年度以降の調査にとって非常に大きな力となる。 今回の調査と前回実施した東京国立博物館所蔵鏡の調査により、朝鮮半島出土多鈕鏡のうち10面の調査を行なったことになる。今後も日本国内の多鈕細文鏡との比較検討および未調査の朝鮮半島出土鏡の調査を行なっていく必要がある。(文責:杉山林継・村松洋介) (扶餘博での写真撮影状況)  (扶餘博での調査風景)  (左側 国立中央博物館 李健茂先生)  |
| このセクションの目次に戻る | 総目次に戻る |