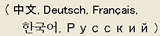| ホーム >> COEプログラム事業の遂行と成果について >> b. 研究会 >> グループ2「神道・日本文化の形成と発展の研究」 研究会「近世の祭祀と儀礼」 | |||
| |||
| 1、開催目的 近世の神道史・仏教史あるいは政治史まで含めた宗教史の課題として大きな影響を持つものに、日光東照宮の研究がある。しかしながら日光東照宮について、これまでの近世史研究の中で十分な検討がなされているとはいえない。そこで今回「近世日光の祭祀と儀礼」というテーマを掲げ、研究会を実施した。 近年、近世史を考える上で分野史を統合する総合史の必要性が指摘され、さらにそのための有効な方法として、社会的通念・常識が成立する「場」の問題に着目した研究が注目されている。このことに即して考えれば、近世における支配思想として山王一実神道と東照宮の存在があり、その社会的実践の場が日光東照宮をめぐる儀礼であったといえよう。そして、それは東照宮信仰として社会に大きな影響を与えたのである。 すなわち、東照宮をめぐる祭祀と儀礼を検討することは、近世の社会理念・常識の再検討のためにも、また現代人の意識形成に大きな影響を与えた国学についての新しいイメージ生成のためにも有効であるといえるだろう。 本研究会においては、根岸茂夫・種村威史、曽根原理・山澤学各氏の報告を中心とした討論により、上述の課題に迫った。なお本研究会は、2005年5月22日開催のシンポジウム「近世日光の祭祀と儀礼」の準備研究会として実施したものである。 2、日時: 2005年5月7日(土) 15時〜19時 3、会場: 國學院大學常磐松2号館第2会議室 4、研究発表者 ※敬称略 根岸茂夫(國學院大學COEプログラム事業推進担当者):「享保期日光社参における将軍の行列」 種村威史(國學院大學大学院博士課程):「天保期日光社参における儀礼の様相」 曽根原理(東北大学): 「『東照宮祭祀と山王一実神道』の構想」 山澤 学(筑波大学):「東照宮祭礼と民衆 ―祭礼成立期を中心に―」 なお、5月22日のシンポジウムでコメンテーターをつとめる澤登寛聡氏(法政大学)にも出席していただき、適宜コメントを頂戴した。 (レジュメ参加) 大友一雄(国立国文学研究資料館史料館):「日光社参と身分―集合記憶と儀礼参加をめぐって―」 5、研究会の詳細 全体の内容は 1根岸・種村両氏の研究発表、 2曽根原・山澤両氏によるシンポジウム準備報告、 3シンポジウムの問題提起・諸問題の検討、であり、それぞれいついて討論が展開された。 5−1 発表概要 5‐1‐1 研究発表 はじめに根岸・種村両氏による、日光社参をめぐる諸問題をテーマとした研究発表が行われた。 根岸茂夫「享保期日光社参における将軍の行列」 本研究会に先立って発表された論文「享保期日光社参における将軍の行列」(『大日光』75 2005)に基づき、さらに盛岡藩南部家の参勤交代の絵巻も利用し、武家の行列の構造を論じた。 種村威史「天保期日光社参における儀礼の様相」 従来の研究の中で、国家権力がいかに人民を動員・編成したかという役論的編成論よりの視覚から捉えられてきた日光社参を、近年深化を見せる儀礼論的視覚より捉え直す必要性を提起した。 その上で天保期の日光社参を素材に、そこに立ち現れる諸種の儀礼、中でも道中における宿城儀礼を中心に検討した。その結果宿城儀礼とは、将軍が大名と主従関係を確認しあう「場」であることを指摘した。さらに近年、政治構造との関係のみでなく、民衆との諸関係、すなわち社会構造との関わりとの中で儀礼を捉える儀礼研究が少なくない。そのような研究動向を顧慮し、報告者は社参中に実施される恩赦、施など、将軍が民衆に関わる施策も儀礼として捉えられる点についても言及した。 5‐1‐2 シンポジウム準備報告 曽根原理「『東照宮祭祀と山王一実神道』の構想」 山王一実神道の中世・近世初期よりの継承・変容過程を、東照宮本地供・東照宮祭礼・東照宮講式・東照宮講を素材として検討する構想を報告した。また山王一実神道の展開についての事例報告も行った。 山澤学「東照宮祭礼と民衆 ―祭礼成立期を中心に―」 日光東照宮祭礼の形成過程・国家儀礼としての特質について、特に伝統的権威(天皇・朝廷)との関わり、次いで祭礼がめざす「治国利民」の思想と民衆との関係を検討する構想を報告した。また東照大権現の融通功徳としての大赦や施をめぐっては、種村報告の内容とも関わって議論が展開された。 大友一雄「日光社参と身分―集合記憶と儀礼参加をめぐって―」 日光社参に関わる諸集団を分析することで、社参の社会的意味を考察する構想が説明された。 5‐1‐3 シンポジウムの問題提起・内容の検討 吉岡孝氏(國學院大學)により問題提起が読み上げられ(具体的内容は「1開催目的」参照)、それを叩き台に内容検討にまで踏み込んだ討論が展開された。 5−2成果と課題 討論においては、研究発表に対しては特に種村報告をめぐり、①民衆をより具体的に射程にいれた儀礼論が展開されて然るべき、②恩赦・施に見られる将軍の政治的実践の背景に存在する思想を、時間軸に沿って検討する必要がある、などの問題が投げかけられた。 以上の討論を叩き台にして特にシンポジウムを射程に入れた討論に移った。曽根原・山澤両氏には、報告のキーワードとなる、山王一実神道、天海の思想、東照宮祭礼についての説明が求められた。シンポジウムの問題提起に関しては、1、2点の訂正以外は出席者に概ね妥当と判断された。さらに、シンポジウムにおける各報告の問題点を確認する作業が行われた。 日光東照宮(あるいは東照宮信仰)については、近世社会のあらゆる場面において大きな影響力をもつゆえ、全体像を語ろうとするとどこかもどかしさが付きまとった。今回の研究会において、特に祭祀と儀礼に焦点を当て、具体的事例に即した各氏の報告と討論が行われたことにより、日光東照宮を理解する手がかりを得ることができたといえよう。 しかし、いくつかの問題もある。例えば曽根原・山澤両氏報告で扱われる宗教的思想と国家理念と、大友・種村両氏報告で扱われる具体的な日光社参の現実的あり方、この両者の乖離をどのように考えていくか、という点がある。具体的には、山澤報告では民衆は「治国利民」を理念とする東照宮祭礼において救済の対象として登場するが、大友報告では社参より排除される集団(出家・浪人・座頭など)の存在が指摘されている。つまり一方では民衆は救済の対象として、もう一方では排除の対象として採り上げられるわけである。このような理念と現実の乖離はむしろ近世の特質をよく表現しているともいえるが、この乖離を5月22日開催のシンポジウム「近世日光の祭祀と儀礼」の中で考えていくことも必要であろう。 さらに、日光東照宮と神道、仏教、儒教、そして国学の諸思想とのかかわり方なども問題となるところであるが、いずれも今後の課題としたい。 (文責 種村威史) |
| このセクションの目次に戻る | 総目次に戻る |