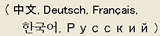| ホーム >> COEプログラム事業の遂行と成果について >> c. 国際会議・シンポジウム >> グループ1「基層文化としての神道・日本文化の研究」 国際シンポジウム「神と神を祀る者―東アジアの神観念―」 | |||
| |||
| 1.開催目的 平成14年度からはじまった國學院大學21世紀COEプログラム「神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成」における研究課題「日本における神観念の形成とその比較文化論的研究」班では、鹿児島県奄美大島(平成15年度)、沖縄県竹富島(平成15年度)、中国貴州省南部トン族(平成16年度)を中心に調査研究を行なってきた。本シンポジウムは、これまでの成果を集大成するために開催された。その内容は、東アジアにおける民俗・文学・歴史・考古といったそれぞれの視点から、神および神を祀る者の検証を通じて、広く東アジアの基層文化としての神観念を捉えようとするものであり、このことは地域性、民族性との関連により形成された神観念を鮮明化することにより、日本の神観念の特質を照射することにも繋がると考える。 2.日時:2005年10月8日(土)〜9日(日) 3.会場:國學院大學常磐松2号館大会議室(8日) 120周年記念2号館2203教室(9日) 4.講演者・発題者・司会等 ※敬称略 ◆基調講演(10月8日 13:00〜17:30) ・講演者 訒敏文(中国社会科学院)「中国・トン族の神観念」 田畑千秋(大分大学)「日本・奄美大島の神観念」 狩俣恵一(沖縄国際大学)「日本・南西諸島の神観念」 廣田律子(神奈川大学)「呼び出された神」 千々和到(事業推進担当者)「中世の起請文に見る神と仏」 ・司会 辰巳正明(事業推進担当者) 飯島一彦(獨協大学) ◆基調講演と発題(10月9日 10:00〜17:30) ・講演者 郎櫻(中国社会科学院)「中国少数民族のシャーマン」 ・発題者 大堀英二(COE研究員)「儒教と神観念」 舟木勇治(COE奨励研究員)「祝詞における神観念」 城粼陽子(事業推進協力者)「神饌と神観念」 青木周平(事業推進担当者)「日本における神判」 飯島一彦(獨協大学)「八重山地方における祭りの『場』の構造ー竹富島を中心にー」 小川直之(事業推進担当者)「来訪神習俗と神観念」 豊島秀範(事業推進担当者)「日本のシャマニズムと神観念」 伊藤好英(慶應義塾大学講師)「韓国の民俗にみる神観念」 吉田恵二(事業推進担当者)「考古学からみた東アジアの神観念」 ・司会 辰巳正明(事業推進担当者) 田畑千秋 5.シンポジウムの詳細 ◆発表概要 訒敏文「中国・トン族の神観念」 この発表は中国南方少数民族の一つであるトン族において、神と人との関係性を明らかにすることを目的とした。講演は、トン族の人が神との交流を実現する媒介者である祭師(シャーマン)の祭祀活動を検討することが中心となった。祭師の来歴と役割は様々であるが、神・鬼と交流する点では共通していると指摘した。そして、トン族社会の多種信仰と万物有霊の伝統的な観念を反映したものと結論づけた。 田畑千秋「日本・奄美大島の神観念」 この発表は奄美大島における神観念の一側面を明らかにすることを目的とした。そこで、「常世」として捉えられるテルコ・ナルコの世界がどのようなものであるのかを再検討した。検討の結果、テルコ神・ナルコ神の言葉は、「照り輝く神・成り輝く神」であるとし、“海の向こう”から来訪する神と位置づける。そして、抽象的な天空世界観よりも古形であるという見解を示した。  狩俣恵一「日本・南西諸島の神観念」 この発表は南西諸島における神観念の一端を明らかにすることを目的とした。そこで、沖縄県の竹富島における神のあり方を中心に検討した。その結果、村落の神(従来からの神)と国家の神という二つのあり方があることを指摘した。この国家の神が生まれる原因として、竹富島が琉球王朝の統治下となり、王府より役人が派遣されるようになったことをあげる。この村落の神と国家の神のあり方は、具体的状況は違うが、仕組みとしては『日本書紀』等にも見出せる可能性があることも指摘した。 廣田律子「呼び出された神」 この発表は中国の祭祀に顕在する「呼び出された神々」を通して、民族性や地域性を反映した神観念の個別的なあり方を明らかにすることを目的とした。そこで、中国湖南省のヤオ族で伝承されている「盤王節」の事例では、強いパワーをもつとされる猛々しい鬼神「五猖」を例に検討した。この「五猖」の荒ぶる力を供物でもてなしたりして味方につけることで、邪悪なものが祭りの場に侵入しないようにまた邪悪なものを退治し安寧を得るようにと目論まれているとする。このような強いパワーを有する神・鬼神は祀り方次第でプラスにもマイナスにも変わるもので、祭りというのは、人々と神との関係を確かめる場であると指摘した。また、ヤオ族は、膨大な文字の経典を持つ民族であり、「五猖」を呼び出す際に読まれる呪詞も紹介された。 千々和到「中世の起請文に見る神と仏」 この発表は日本中世における人々と神・仏の関わり方の一側面を明らかにすることを目的とした。そこで、人と人が約束をとりかわすときに、神仏を仲立ちとした誓約を記す起請文のあり方を検討した。起請文は、神と人との交流の中で成立するもので、起請文の趣旨が神へ伝わったことを実感することで効力を持つものであったと指摘した。しかし、中世末になると、1606年に行なわれた鉄火の記録に代表されるように「勝負」の性質を強くし、神々が立ち会う神判としての性質がなくなったとも指摘した。  郎櫻「中国少数民族のシャーマン」 この発表は中国におけるシャーマンと神観念がどのように現れているのかを明らかにすることを目的とした。そこで、女神信仰やシャーマンの歌舞、そして口承史詩(シャーマンが儀式で歌う歌)に見るシャーマンの有り様を、中国少数民族のいくつかの事例をもとに検討した。史詩を中心にしたシャーマンの演唱儀式には、多くの原始文化の要素を保留していることが明らかとなった。また、シャーマン文化研究、神観念研究において貴重な資料となる口承史詩の演唱活動も現在は衰微と消滅過程にあり、早急に保存を必要とするという課題も提示された。 大堀英二「儒教と神観念」 この発表は上代日本において、国家の祭祀や神観念に対して儒教はどのように関わったかを追求することを目的とした。そのため、『日本書紀』と中国史書を比較し、神と人との媒介者である「巫覡」が『日本書紀』でどう描かれているかを検討した。その結果、中国漢代の儒教国家の史書と向き合うことにより生み出された神観念の一つのあり方として「巫覡」を見ることができると指摘した。 舟木勇治「祝詞における神観念」 この発表は神への言葉である祝詞における神観念を明らかにすることを目的とした。その手がかりとして、『延喜式』所収の「六月晦大祓」祓戸四神条の文脈の考察を行った。祓戸四神条に記紀には見られない神々が登場することに関して、そこでは神話の再生が図られており、大祓詞全体の効果を高める意図があると指摘した。  城粼陽子「神饌と神観念」 この発表は人と神との関係性を神饌を通じて明らかにすることを目的とした。「神饌」には、「捧げる」ことで神に服属を示し、そのものの付加価値を高めることでその服属を強固に保証する図式と、「神饌」の伝承をもって祭儀と祈願の正当性を保証する図式が内在することを指摘した。また、神に「神格」が認められることで「神饌」にも「好物」などの性格付けが行われることも指摘した。 青木周平「日本における神判」 この発表は人間と神との誓約がどのように行われるかを明らかにすることを目的とした。そのため、記紀の「盟」と「誓」の用例を検討し、〈神判〉の具体的あり方を検証した。〈神判〉とは、神に対して判断を請うもので、神意に反した場合、刑罰が科せられるものであると指摘した。そこに、社会秩序と関わる問題があることも提示した。 飯島一彦「八重山地方における祭りの『場』の構造ー竹富島を中心にー」 この発表は祭祀において、人と神がどのように向き合うのかということを明らかにすることを目的とした。そこで、八重山の御嶽における女性(カンツカサ・巫女)と男性の関係を中心に祭りの「場」を検討した。祭りの「場」を共有しながら、別々な振る舞いを堅固に維持できるのは、行動が規範を生み出す意識構造が共有されているからだと指摘した。  小川直之「来訪神習俗と神観念」 この発表は来訪神習俗を通して日本文化の基層に存在する神観念を追求することを目的とした。そのため、折口信夫博士の「まれびと」研究を整理し、来訪神の具体的事例を検討した。来訪神の位置づけは、研究者により多岐に渡る現状を受け、異形の身体性を持つ神に限定するのか、観念的な訪れ神も含めるのかなどといった、来訪神の概念そのものを再検証する必要があることを指摘した。 豊島秀範「日本のシャマニズムと神観念」 この発表は東北地方を中心としたシャマニズムと神観念との関係性を明らかにすることを目的とした。そこで、イタコとカミサマ(ともに巫者だが、役割が異なる)の入巫過程と現在の実態を検討した。そして、現在、イタコが消えつつあるという問題を提示し、その理由として、巫者をとりまく現代の社会的状況の変化と、それに伴い、神に対する認識がイタコからカミサマへと移りつつあることが原因であることを指摘した。 伊藤好英「韓国の民俗にみる神観念」 この発表は韓国の神観念の一側面として、村落祭儀における神観念がどのようなものであるのかを明らかにすることを目的とした。そこで、村落祭儀(マウルック)の実態を具体的に検討した。韓国の村の神は、その姿が多様であるが、その神の具象化には、巫俗の影響が認められることを指摘した。 吉田恵二「考古学からみた東アジアの神観念」 この発表は遺跡・遺物を通して、基層文化の神観念を明らかにすることを目的とした。そこで、新石器時代から古代までの日本を中心に、一部中国を含めて「祭祀遺物」を検討した。「祭祀遺物」と呼ばれるものが仏教関係遺跡からほとんど発見されていないことから、仏教以外の祭祀において使用されたものであろうということを指摘した。  6.討論 1日目(8日)のディスカッションでは、まず、祭祀における言葉と文字の経典との関係性について論議された。トン族やヤオ族そしてナシ族などの中国少数民族を中心として、シャーマンが唱える言葉が漢字の導入により文字化されるが、その経典は知識を持つシャーマンのみに理解されるものであることが確認された。そして、その言葉と文字の関係は、中華文明とその周辺として、トン族、ヤオ族、ナシ族のみならず、日本本土や奄美・沖縄にも同様のあり方が見て取れるということにも議論が及んだ。 そこで提示されたのが、狩俣氏の報告を受けた国家の神祭りと村落の神祭りの問題であった。例えば、ニライカナイというのは、久高島を通った東方にあり、そこから神がやってくるという考え自体が、国家の指導のもと整理された形のものだと指摘された。さらに、単純にすると、神迎え、祈り、そして神送りという構造化さたものが国家により形成され、その主導に基づく神祭りだと指摘された。 また、千々和氏の報告を受け、中世の起請文は、時代が進み、国家との関わりが強くなるにつれて、儀礼的に形式的になっていく様が確認できることが指摘された。 2日目(9日)のディスカッションでは、1日目と2日目で講演・発題者全員が2日間全体を通して問題を考えるという体裁をとった。そこでは、前日の東アジアにおける各地域の神祭りの有り様から出た問題を、シャーマンを中心に再検証することを主に行った。 まず、郎氏の報告を中心に中国少数民族における文字の経典を持つシャーマンという点で質疑がかわされた。そこでは、シャーマンたちは基本的には口承で、文字の経典には権威としての役割があるのではないかという問題が提示された。 次に、飯島氏、そして1日目の田畑氏と狩俣氏の報告を中心に琉球王朝の神祭りとその周辺の神祭りの関係性について質疑が交わされた。そこでは、文字の経典の問題も含め、国家が形成されることによりその周辺の神祭りも形式化するという問題が提示された。それは沖縄地域だけの問題でなく、東アジア全体の問題へも繋がるものであり、また『日本書紀』、祝詞という古代の文献から中世の起請文への繋がりをどう考えるかという問題にも繋がるものと指摘された。 そして、今回の質疑の中心は、シャーマンを中心に口承と文字化の問題をめぐって論議がなされた。そこでは、宗教体験をどのように文字で表現するのかという問題を一方で抱えながら、伝承ということでは神の歌や祭りの歌などは口承の形を取るものであり、どのように口承されるかを説明することで、神祭りがどうシステム化されてきたのかが明らかになるのではないかという指摘もなされた。  7.成果と今後の課題 今回の「神と神を祀る者―東アジアの神観念」シンポジウムでは、東アジアの各地域の神祭りを検証することができた。そして、その各地域の神祭りがシャマニズムを基本としたもので、東アジアの中で普遍的に現れているものであることが確認された。さらに、東アジアの中で普遍的に見られる神祭りを対象に、①口承と、その内容を文字化することでの経典という問題、②口承としてシステム化されているという問題、③システム化された神祭りが国家の祭りとしてどう展開していくのかという問題、④東アジアの中での神祭りがシルクロードを接点としてギリシャ・ローマとの関係性を深める可能性等、いくつかの問題が提示された。今後は、神にどう接し、神をどのように崇め敬い、そしてどのように神を祀ることによる文化を形成してきたのかという文化形成論の問題への展開が重要な課題となろう。 文責:大堀 英二(COE研究員) |
| このセクションの目次に戻る | 総目次に戻る |