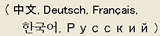| ホーム >> COEプログラム事業の遂行と成果について >> a. 調査 >> グループ1「基層文化としての神道・日本文化の研究」 中華人民共和国における新石器時代偶像調査 | |||
| |||
| 中華人民共和国における新石器時代偶像調査 第Ⅰグループ 基層文化としての神道・日本文化の研究グループ 1.調査地 中華人民共和国山東省:山東省文物考古研究所・山東大学・山東大学博物館 2.調査参加者 吉田恵二(事業推進担当者) 加藤里美(事業推進協力者・日本文化研究所専任講師) 山添奈苗(COE研究員・國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期) 高野晶文(國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期・北京大学考古文博院高級進修生) 新原佑典(國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程前期) 加藤夏姫(國學院大學大学院文学研究科史学専攻博士課程前期) 3.出張期間 平成18(2006)年7月30日〜同8月9日(11日間)10泊11日 4.調査の目的と成果 本調査は、日本列島における祭祀活動の実態を東アジア史的観点から考古学的に位置づけることを目的とし、中国新石器時代の人や動物を象った偶像に焦点を当て、日本列島との比較検討を行なうための基礎資料収集として実施した。平成16・17年度に、日本列島弥生文化の故地とされる山東省と遼寧省において、新石器時代偶像と同時代資料の調査を実施しており、山東省出土偶像についてはその殆どの調査を完了した。 今年度は、山東省出土から出土した偶像の出土遺構の種類、及びこれに伴う遺物の調査を行なった。その結果、龍山文化期の尹家城遺跡50号土坑から出土した猪形石製品については、使用によって破損した後に土坑に廃棄されたことが明らかとなった。 他方、小型双耳壷は大汶口文化期には墓に副葬するための明器として確立されているが、これに先行する北辛文化期では土坑から出土する非常に精巧な作りで実用的なものと、墓から出土する粗雑な作りで形骸化したものとの両者に分かれる可能性が明らかとなった。形骸化は双耳に顕著に現れており、本来貫通するべき孔が貫通せず、明器化したものと考えられる。このことから、山東半島では土器の明器化は北辛文化期に始まり、大汶口文化期に確立したことが判明した。また、大汶口文化期には「祭」に特化した偶像と、「葬」に特化した明器が並存する一方、これに先行する北辛文化期には「葬」に用いる明器は存在するものの偶像が未発見である現象をどのように解釈するかという新たな問題が浮上してきた。 (文責:吉田恵二・山添奈苗・新原佑典)   山東省文物考古研究所  山東大学 |
| このセクションの目次に戻る | 総目次に戻る |