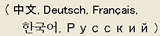| ホーム >> COEプログラム事業の遂行と成果について >> e. 成果刊行 『修験道の地域的展開と神社』(神社と民俗宗教・修験道研究報告2)の刊行 | |||
| |||
| *本書は在庫切れのため、頒布を終了しました。 [書名]國學院大學21世紀COEプログラム成果報告書『修験道の地域的展開と神社』(神社と民俗宗教・修験道研究報告2) [内容] 國學院大學21世紀COEプログラム・第Ⅱグループ「神道・日本文化の形成と発展の研究」の一環として、平成17年度「神社と民俗宗教・修験道の研究」成果報告書(事業推進担当者・宮家準)を刊行しました(2006年2月28日発行、A4判、288頁)。 平成17年度の本研究は、近世の里修験(地方修験)と神社の関係を研究テーマとしました。近世の地域社会に定住した修験者(里修験)は、本山派・当山派・羽黒派・英彦山派などに属し、巫術、加持祈祷、配札、先達などの活動を行ない、あわせて地域の氏神や小祠などの祭祀をゆだねられることも多くありました。本研究では、こうした活動の実態把握と分析をねらいとしました。 本報告書の具体的内容は、第1部では、近世の熊野・伊勢・金峰など中央の霊地の修験者・比丘尼の勧進や唱導活動を跡づけた宮家の諸論文と、本山派・当山派・英彦山派の修験者の書上を収めています。第2部では、まず第1章で中世の熊野先達・檀那、近世の本山派・当山派・羽黒派の修験の全国分布を挙げました。次章以降は、近畿・関東甲信越・東北・中部・中国四国・九州の順で各国ごとの熊野先達、本山派・当山派・羽黒派・英彦山派の修験と彼らが別当等を担った神社ならびに山岳信仰関係神社の概説と、本研究に参加している共同研究者が執筆した関係論文を収録しました。また、各章(各地方)ごとに、国ごとの熊野先達・檀那、本山派・当山派・羽黒派の修験と修験関与の神社のリストを、各国の地誌、藩の書上、教団史料をもとに作成して掲載しました。 [目次] 『修験道の地域的展開と神社』(編集:宮家準) 序 第I部 中央霊地の修験とその地域的展開 第1章 熊野の修験・比丘尼(宮家) 第2章 伊勢の山伏と比丘尼(同上) 第3章 金峰山の勧進と穀屋(同上) 第4章 蔵王権現信仰の伝播(同上) 第5章 教派修験の地域的展開〔史料データ〕(作成:久保康顕、山口正博) 第II部 全国各地の霊山・修験・神社 第1章 全国の霊山・修験・神社(宮家) 第2章 近畿 第1節 近畿の霊山・修験・神社(宮家) 第2節 中世後期東大寺堂衆と咒師(大東敬明) 〔史資料データ〕 第3章 関東甲信越 第1節 関東甲信越の修験と神社(宮家、久保、森悟朗、上野力) 第2節 関東における木曽御嶽講の展開と性格(中山郁) 〔史資料データ〕 第4章 東北 第1節 東北の霊山と修験・神社(宮家) 第2節 菅江真澄が見た東北の里修験(永吉慶子) 〔史資料データ〕 第5章 中部(東海・北陸・伊勢・伊賀・志摩を含む) 第1節 中部の霊山・修験・神社(宮家、精園佳子) 第2節 遠州の秋葉山と修験(河村忠信) 第3節 遠州森町の飯田院内村について(谷部真吾) 〔史資料データ〕 第6章 中国・四国 第1節 中国・四国の霊山・修験・神社(宮家) 〔史資料データ〕 第7章 九州 第1節 九州の霊山・修験・神社(山口) 〔史資料データ〕 |
| このセクションの目次に戻る | 総目次に戻る |