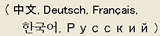| ホーム >> COEプログラム事業の遂行と成果について >> b. 研究会 >> グループ1「基層文化としての神道・日本文化の研究」 第5回 「神観念形成」研究会 | |||
| |||
| 第5回 COE「神観念形成」研究会報告 日 時 平成15年10月12日(日)午後4時から 場 所 常磐松2号館3階第2会議室 参 加 者 野村純一(COE事業推進担当者)、辰巳正明(COE事業推進担当者)、青木周平(COE事業推進担当者)、小川直之(COE事業推進担当者)、田畑千秋(大分大学教授)、城崎陽子(COE研究員)、長野隆之(COE奨励研究員)、大堀英二(本学大学院生)他 報告内容および報告者 神を迎える−奄美龍郷町秋名のアラセツ(ショチョガマ・ヒラセマンカイ)と沖縄竹富島のユーンカイに関する神迎え神事調査報告― 國學院大學兼任講師・COE研究員 城 崎 陽 子 COE第Ⅰグループ「基層文化としての神道・日本文化の研究」における研究課題「日本における神観念形成とその比較文化論的研究」では、日本人の神観念に関する調査研究の一環として奄美大島龍郷町秋名の「ショチョガマ」「ヒラセマンカイ」の両行事と沖縄竹富島の「ユーンカイ」行事の調査を平成15年8月29日から9月6日にかけて行った。本研究会はその調査内容の報告と考察、ならびに今後の研究課題について共通の認識を図るために広く一般に公開されて行われた。 調査に先立つ打ち合わせの中で、この度の調査においては奄美・南琉球における「神観念形成」という命題に迫る視点として以下の6点が挙げられた。 1,奄美アラセツ行事における神観念 2,沖縄竹富島ユーンカイにおける神観念 3,神口の表現と神観念 4,歌掛けと神迎えにおける神観念 5,儀礼食と神観念 6,聖地の形成と神観念 これらを当面の問題意識として、各行事における「神観念」の類似点・相違点、さらには「日本における神観念形成」の一端を探ることが、今回の調査の目的であった。 報告は大きく二つの部分から成り立っていた。一つは、ショチョガマ・ヒラセマンカイおよびユーンカイの各行事について行事の概要と経過を報告する部分と、調査事項の中でも特に「神観念形成」に深く関与していると考えられる「ノロ」「神司」の行事における役割とその成巫過程、および、「神口」の表現と神観念との関わりを考察した部分である。なお、詳細については、國學院大學21COEが公開している各調査の報告に譲る。 リンク:奄美大島ヒラセマンカイ調査報告 リンク:竹富島ユーンカイ調査報告 報告では、このたびの調査の成果として、まず第一点に奄美・南琉球における司祭者としてのノロおよび神司に関わる神観念の具体相をうかがうことができたことがあげられた。また第二点としては神口を通じて神と人との交流の様を具体的に確認することができたこともあげられた。 以上二点に集約される成果は今後、神観念の中でも、神と人がどのように位置づけられ、かつ、どのように交流するかという点を考える上で有効な資料となることが確信される。また、神話や神謡といった文献から神観念を抽出するという作業と実地調査による神観念の採集との連携の必然性を示唆する調査内容となったことは意義深いことと考える。 奄美・南琉球の調査においては、当然のことながら琉球王府との関連が深く、ひいては中国南東部と琉球王府との交流史のなかでの比較調査の必要性を強く感じると同時に今後の課題の方向性を見通す報告であった。 文責:城崎陽子 |
| このセクションの目次に戻る | 総目次に戻る |