対象物の空間的な関係づけへの道程
その2─終点の状態の確認と先取りの萌芽─
柴田保之
目 次
はじめに
1.対象への到達における終点の状態の確認と終点の先取り
(1)空中への到達において
(ア)終点の状態の確認から視線の移し換えへ
(イ)視線の移し換えと運動の調節
(2)たどっていく到達的運動において
(ア)終点の状態の確認
(イ)到達的運動に伴う触覚によってとらえられる空間的関係
2.対象の操作における終点の状態の確認と終点の先取り
(1)操作的運動と視覚
(ア)視覚による終点の状態の確認と先取りの出現
(イ)視覚による終点の先取りと空間的関係の受容
(2)操作的運動と触覚
(ア)対象を操作する手と同一の手の触覚において
(イ)対象を操作する手と反対の手の触覚において
(ウ)触覚的役割と運動的役割の転換について
おわりに
はじめに
本稿では、前稿(柴田、1993)に引き続き、ある物を穴や容器に入れるというような行為に代表される二つの対象物を関係づける操作が可能になるための基本的な要件である終点の空間的な先取りにおいて、それが終点の状態の確認の中からどのように生まれてきて、運動の調節に関与するようになるのかということについて、障害の重い子どもたちとの実践的なかかわり合いの事実に基づきつつ考察を加えていきたい。
前稿における考察の最後に、視覚や触覚が、終点の位置や方向の先取りにつながるものへと発展するために重要なのは、終点の状態の確認であることについて簡単に述べた。この、終点の状態の確認から終点の先取りが生まれてくる経過については、その運動の具体的な内容によって二つに大きく分けることができる。すなわち、これまで行ってきた運動の区別である対象への到達的運動、対象の操作的運動、対象の取得的運動という区別に従えば、一つは対象への到達運動であり、一つは対象の操作的運動と取得的運動を合わせたものである。
操作的運動と取得的運動では、その目的が異なるわけだが、ここで扱う範囲では、操作的運動における終点までの経過と、取得する対象が抜き取られる地点までの経過は、抵抗に対ら、運動がさらに継続されるところまでを考えれば、操作的運動は、まだ教材から離れない状態で継続されることが可能であるのに対して、取得的運動ではいったん離れてしまう。したがって、取得的運動の場合には、空間的に離れた対象の関係づけというものを含むことになる。そして、前稿では、そのこともふまえて考察を進めたため、操作的運動と取得的運動とを区別してきた。しかし、今回は、空間的に離れた対象の関係づけの問題は、次回の考察に回すので、両者を一括して、取得的運動は操作的運動として扱うこととする。
また、前回、操作的運動の一つとして考察を加えた放す運動も、これは、そのまま空間的に離れた対象の関係づけの問題につながっていくので、次回の考察に回すことにしたい。
さて、終点の状態の確認とは、運動と一体になって起こっている触運動感覚的な運動の終了の確認とは別に、視覚や触覚によって終点の状態を確認するということである。すなわち、手の運動や手が操作している対象を受容するだけでなく、終点にある対象と、手や手が操作している対象との空問的な関係をも受容するということになる。そして、この終点の状態の確認は、この時点では、運動の目的の達成のための必要条件として要請されるというよりは、自分の身体も含めた外界のできごとを積極的に受容しようという感覚の側の要因によって生まれるものと考えられる。したがって、運動の遂行という目的が必然的に要請するものは、終了したということの確認ではあっても、必ずしも終了した状態を改めて確認しなおすことが必要なわけではない。そういう意味では、運動を遂行する目的に対して、運動が終点に達する際の空間的な変化に対する興味というものが、新しい目的として生まれてきたということができるだろう。そして、その興味が強いものであれば、もともとの運動の目的は背後に退いて、その空間的な変化自体を再現するというように発展することもありうると考えられる。
こうして得られた終点における空間的な変化を受容しようという感覚の新しい使い方は、遂行中の運動をより調節されたものとするだけでなく、新たに、より高次の運動の遂行のための手段として組み込まれていくことにもなる。そして、そうした空間的な変化を受容する感覚の使い方は、その運動の遂行にとって不可欠のものとなっていくと考えられる。
1.対象への到達における終点の状態の確認と終点の先取り
対象への到達においては、空中に手を伸ばしていくという到達的運動と、何かをたどるという到達的運動とを区別することができる。そこで、まず、空中の到達的運動から見ていくことにしたい。なお、対象の到達においては、対象物は一つであって、二つの対象の関係づけということにはなっていない。しかし、二つの対象の関係づけに密接にかかわる感覚による先取りと関係が深いため、これまで論じ残してきた問題であったので、本稿では、まずこの到達的運動から問題にすることとしたい。
(1)空中への到達において
(ア)終点の状態の確認から視線の移し換えへ
対象の存在が、何らかの感覚的な受容によってとらえられ(対象を見る、対象の発する音を聞くなど)、そのことがきっかけになって手を空中に伸ばして対象に到達する場合、ここでは終点の空間的な状態は、離れていた手が対象と接触したということになり、その状態を確認する可能性のある感覚は、運動自体に伴う触運動感覚と、視覚であるが、触運動感覚については、触れた時点ですでに到達的運動は遂行されたことになるので、そもそも先取りということを考えることはむずかしい。したがって、ここでは、もっぱら視覚による終点の状態の確認について考えていくことにする。
また、視覚は、手の運動に同調してそのまま追い続けて終点に到達し、そこで改めて対象の存在を受容するということが起こるという場合と、運動をする前に対象の存在を受容してからそのまま対象を見続けているところへ手が対象に到達し、そこで改めて手を受容するという場合とを考えることができるわけだが、運動に先立って対象が存在するということを受容して運動にきっかけを与える感覚は、視覚であることが多いことに加え、聴覚や嗅覚によって対象の存在が受容されても、それが直接運動に結びつく前に、その存在を視覚によって受容してから運動を起こすことになると考えられるので、むしろ前者よりも、後者の方を考える方が現実性が高いだろう。
したがって、終点の状態の確認は、対象を視覚がとらえることによってきっかけを与えられ、漠然とした方向が先取りされた運動が対象に到達した時に、その運動の遂行中ずっと対象をとらえ続けていた視覚が、対象に手が接触した状態をとらえるというところから始まるということになる。(註)なお、到達運動という目的が達成されて運動が終了したということの確認は触運動感覚によってなされるわけであるが、ここでは、その触運動感覚によって運動の終了が確認された上で、終点の空間的な状態の確認が起こることになる。こうした終点の空間的な状態の確認は、初めは運動が終了してしまった静的な状態の受容で、視線のはっきりした移し換えを伴わずにほぼ同時に受容されるものであるが、その中には、手と対象が接触する直前から接触するまでの動的な過栓の受容も含まれるようになると考えられる。
こうした到達運動が達成される際の動的な過程の受容から、手と対象との間の視線の移し換えというものが起こると考えられるが、ここには、二つの場合があると考えることができる。すなわち、今述べてきたように、到達運動が首尾よく達成される場合で、この時は、到達する直前に対象と手の両方に同時的に注がれていた視線が、しだいに到達する前の手の方へ注がれるようになっていき、継時的な視線の移し換えになっていくというものである。他方、到達運動が失敗した際に、その失敗した手が対象の近くにある時、その手に視線を移し換えるということも起こると考えられる。到達の失敗は、視覚が漠然とした方向の先取り以外にその運動の遂行中に調節に参加していない段階では、いったん運動が始められてしまうとその調節に必要な手がかりが存在していないため、手の届く範囲に対象があっても大いに起こりうるのである。いずれにせよ、こうした過程の中から、しだいに対象から手への視線の移し換えが起こり、その移し換えも、しだいに、時間的にも空間的にも隔たった移し換えへと発展し、さらに、一方通行的なものから、往復運動的なものへと発展していくと考えられるのであるのである。
ところで、このような視覚による対象や手の運動の受容は、対象や手の運動を受容すること自体が目的であるところから生まれるものであって、最初から運動を調節するために生まれるものではないと考えておいた方がよいと思われる。それにもかかわらず、こうした視線の移し換えが、単に視覚の側からの興味だけではなく、運動の調節に一定の役割を果たすようになっていくわけであるが、そこには、到達運動に失敗した際の視線の移し換えが関係しているということは言えそうである。なぜなら、到達できた場合、漠然とした方向の先取り以上に、視覚が運動の調節に参加する必要はないわけであるが、いったん到達に失敗した場合には、視線が対象に注がれることが運動の続行のきっかけになるし、失敗したことが新たな運動の工夫をもたらす場合に、視覚による対象や手の受容が、その工夫に利用されるということが起こりうるからである。
ただし、一般に新しい行動の出現に対して、その行動がある目的の遂行のための必要から生まれるという考え方があるが、ここでもしそのような考え方に立てば、対象への到達を先取りして調節する視覚の働きは、こうした到達の失敗の繰り返しの中から生まれることになる。そして、教育的な働きかけとしては、ある対象の到達が適度に困難な状況で繰り返し到達運動をさせること、もっと具体的に言えば、容易には到達しえないところに欲しい物を繰り返し提示することが、視覚による到達運動の調節を生むという考え方をもたらすことになる。だが、すでに述べたように、終点の状態の確認という見ること自体が目的となる状況の中で用意されてくると考えられるのである。もちろん、このような失敗の経験の中でよりよい運動の調節が工夫されると考えられるが、それは、あくまで終点の状態の確認という、見ること自体が目的となることを前提として起こると考えた方がよいと思われる。
(イ)視線の移し換えと運動の調節さて、手と対象の間の視線の往復的な移し換えというものが起こるようになるところまで述べてきたわけだが、それだけでは、それが運動の調節にかかわることになるという保証があるわけではない。視線の移し換えの中で一体何が受容されているのかということが問題となってくるのである。手と対象という二つのものを見ただけであるならば、それらは孤立した二つの実感だけが受容されたにすぎないことになる。だが、それでは運動の調節に必要な方向や位置や距離というようなものはとらえられていない。したがって、手と対象の間の空間的な関係である方向や位置や距離が受容されなければならないのである。
ここで、いささか話が前に戻ることになるが、視覚的な受容に基づいた運動の調節の一種であると考えられる漢然とした方向の先取りが起こるのは、運動が起こる前に視線が対象にいったん注がれて運動が始まればそのままそれてしまうという状態や、さらに進んで運動の遂行中にもしだいに視線が対象からそれないようになっていくという状態、そして、手が対象に到達するところも受容されるようになっていくという状態においてであった。これらのいずれの場合も、対象に視線を注ぐことによって作られる対象への身構えの姿勢が、手の運動方向を漢然と先取りして、運動の調節に関係していると考えられる。だが、これは純粋に視覚の内容によるものではない。それでは、このようなまだ二者の見比べを含まない受容の内容そのものは、何ら運動の方向づけには役に立たないのだろうか。確かに、二者の受容ではないので、方向や位置、距離といった関係がそこに受容されているとは言いきれない。しかし、こごには、対象が主体から隔たりをもったものであるということが視覚的に受容されており、その隔たりは、主体によって到達運動を必要とするものとして意味を与えられて、その到達に要する運動の大きさの実感が、隔たりの大きさの意味づけをもたらしていると言えるのではないだろうか。そして、これは、奥行きの次元の原初的な受容ということができるかもしれない。視覚的な受容の内容には、その隔たりの遠さや近さということが含まれている可能性もあるし、含まれていないのかもしれない。しかし、いずれにせよ、原初的な奥行きの次元における隔たりの受容と言うものを、空間的な関係の視覚的な受容の始まりのところに想定しておくことは意味があるように思われるのである。
このように二者の関係としての空間的な関係以前の奥行きにおける隔たりの受容から、視線の移し換えが生まれることによって、二者の関係としての空間的な関係の受容が始まると考えられる。それでは、この二者の関係である手と対象の関係は、どのようなものとして受容されているのであろうか。
私たちは、二つの対象の空間的な関係を考える時、知らず知らずのうちに、基底にある水平面や対面する垂直面上にあたかも投影されるような関係としてとらえることが多い。ところが、ある物に向かって手を出す場合にも、その位置は、基底にある水平面や対面する垂直面の上にあたかも投影されるような関係によって手を伸ばす方向や距離を決めているように思われる。確かに、いわゆる両眼視差など、その物自体の視覚像から得られる情報の役割も小さくないが、例えば、地面や床といった基底面が全く視野に入らない状態で物を見ると、奥行きの関係を浮かび上がらせるはずの基底面への投影的なとらえ方ができないため、位置関係はとらえにくいということがあるのである。
こうした私たちの視覚的な空間関係の受容の仕方に対して、ここで考察しようとしている状況において受容されているものはいささか異なるように思われる。なぜなら、そうした平面上への関係の投影的なとらえ方は、基底面や垂直面というようなものを構成していく様々な操作、すなわち平面上での対象の操作に視覚が参加していく結果として起こってくるものと考えられるからである。
ここでは、まだそうした平面上での対象の操作に視覚が参加している状況ではないため、視覚的に受容された二者の関係は、平面上に投影されるかのようにとらえられるものではないと考えられるのである。
それでは、ここではどのようなものとして二者の関係はとらえられているのだろうか。手と対象の関係は、私たちのとらえ方で言えば、基底面上に投影されるような奥行きの次元における遠近の関係と、対面する垂直の平面に投影するかのようにしてとらえられる上下と左右の関係ということになるが、そのようなことが起こっていない時には、こうした関係は、視覚によって受容された手と対象の間には直接は見えてこないものである。なぜなら、視覚的に受容される対象と手は、実際には到達していない場合でも重なってしまう場合もあるし、また、対象と手が離れて見える場合においても、視覚によって受容される対象と手の間の隙問は、対象と手の実際の距離を表しているわけでもないからである。
したがって、この時点では、奥行きの次元に関しては、今述べた、対象に視線を注ぐことによって漠然とした方向の先取りを行う場合と同じく、隔たりとしての奥行きの存在が受容されるということである。それは、重なって見えてもそれが到達したのかどうかは触覚的にしかわからないし、手と対象の間の空隙は、それだけでは距離についての情報を含んでいないわけで、奥行きの次元では、手の運動の調節に役に立つ視覚的受容の内容はほとんど含まれていないと言ってもよいだろう。ただし、両眼の視差や見慣れた対象の大きさ等の区別によって少しずつ奥行きの次元における遠近の関係の受容ができるようになるという可能性はないわけではないが、そうした手がかりも基底面上の配置として投影的にとらえることによって、明確な奥行きとしての意味がもたらされるとも言えるわけで、そうしたとらえ方が存在していない状況では、それらも非常に未分化なままにとどまると考えられる。
一方、上下左右と言った関係に関しては、対象に向かって手が伸ばされてない場合には、その間を視覚的にとらえても、手をそのまま上下左右に動かしても対象には到達しないわけだから、それは運動の調節には役立たちにくいが、いったん起こした到達運動が失敗したというように、対象に手が近づいたのに、対象と接触が起こらない時、手と対象の間を視覚的にとらえることは、運動の調節に役立つ可能性をもっていると言ってよい。つまり、左にずれていればもう少し右に手を動かすというような調節の可能性が出てくるのである。
それでは、このような調節においては、いったい何が受容されているのであろうか。まず、当然のことながら、この関係は、二者の問に成立するものなのだから、その間が何らかのかたちで視覚的に受容されなければならない。視覚的に受容すると言っても、視線が注がれてしまうとそれは問ではなく一つの対象になってしまうので、この間というのは、特に視線を注がれるわけではないが二つの対象の背後に漠然と受容されるものということになる。
また、この間の受容が運動の調節につながるためには、手と対象の間が直線でつながる関係であるということが受容されなければならない。しかし、実際にはその間に直線が存在するわけではない。では、どうしてその空虚とも言える間に直線でつながるという関係が受容されうるのだろうか。それは、おそらく、二者を受容する眼球運動自体が直線的な動きをするということもあろうが、二つの間が運動によって直線的につながるということを受容することを繰り返していく中で、運動によって実際につながれる前に運動の軌跡の予測が起こり、そこに直線でつながる関係というものが見えてくるようになるのではないかと考えられる。そして、この直線でつながる関係として受容されたものと、手の運動との対応関係が到達運動を繰り返す中から作られてきて、その関係の受容が運動の方向を調節するようになると考えられる。
以上、手と対象との問の視線の移し換えということが起こってくることによってもたらされる運動の調節について考察を加えてきた。こうした状況は、さらに、すでに述べたような、上下左右の次元が垂直面に投影しうるような関係として受容されたり、奥行きの次元が基底面に投影しうるような関係として受容されたりするようになって、到達運動の調節はより高次なものへと発展していくと考えられる。しかし、こうした垂直面や基底面といった平面上の関係としてとらえられるようになるには、単に到達運動を繰り返していただけでは不十分であり、実際の平面上で対象物に働きかけるということが必要となると考えられる。そうした運動を含む操作的な運動や取得的な運動を通して、対象物の関係は、平面に投影されるような配置としての関係としてとらえられるようになってくると考えられるのである。
(2)たどっていく到達的運動において
次に到達的運動の一つとして、空中へ手を伸ばしていく到達の次に面上の手がかりを利用してたどっていく到達的運動について述べることにする。
(ア)終点の状態の確認
たどっていく到達的運動においては、終点の確認として、視覚と触覚の両者について考えることができる。視覚については、終点の状態の確認については、目的となる対象へ到達するという状態の確認であるから、上で述べた空中での到達における場合と同様になるので、ここでは省略する。また、そうした終点の状態の確認から先取り的な状況が生まれてきて、
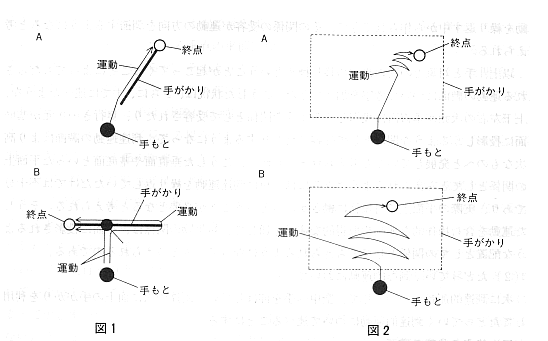 それが運動の調節に関与するようになると、到達という目的を遂行することのみであれば、あえてたどるのではなく、空中への到達的運動に移行する可能性が高いと考えられる。そこで、ここでは、触覚との関係について考えていくこととしたい。
それが運動の調節に関与するようになると、到達という目的を遂行することのみであれば、あえてたどるのではなく、空中への到達的運動に移行する可能性が高いと考えられる。そこで、ここでは、触覚との関係について考えていくこととしたい。
たどるという到達的運動は、どのような手がかりをもとにするのかということで、その運動を区別することができる。すなわち、棒や溝、縁というように線状の手がかりに基づく場合と、机や事物の表面というような面状の手がかりである。
前者の手がかりの場合、さらに、手もとと目的の対象とが1本の線で結ばれるような場合と、線状の手がかりの中間に触れたところでどちら側に進むかという二つの選択肢があって、いずれか一方の端に目的の対象がある場合とである。1本の線で結ばれる場合には、手前から遠ざかっていく方向に運動を続けていくとその先に対象があることになり、運動としては1方向の運動になる(図lA参照)が、手がかりの中間に触れたところから始まる場合には選択した方向に目的の対象がなかったら戻るという往復運動が必要になる(図1B参照)。
後者の手がかりの場合、大まかな方向づけが視覚的な受容や既知の状況での慣れから得られている場合には、ある程度直線的に伸びた後、肘を中心にした弧状の往復運動を起こしながら向こう側へ進んでいくというような到達的運動が起こることになり(図2A参照)、全く方向づけが得られない場合には、初めからそうした弧状の往復運動を起こしながら向こう側へ向かって手を伸ばすことになる(図2B参照)。
こうした到達的運動は、線状の手がかりであれ面状の手がかりであれ、手がそれらの手がかりに触れているという状況を受容しながら、そこから外れたり離れたりしないようにして、終点の対象に到達するという意味で触覚による調節をたえず受けており、それは、到達していない状態から到達した状態への変化をも受容しているという意味において、結果的に、離れていたものが接触するという終点の空間的な状態の確かめを行っていることにもなっている。
ただし、先取りということに関して言えば、たどるという到達運動とそれを調節している触覚は一つの手の運動の中に同時に存在しているので、触覚だけが運動を先取りするということはありえない。触覚が終点に触れた時には運動も同時に終点に到達していることになるからである。
しかし、見方を変えれば、こうしたたどるという到達運動は、両手の役割の分化と協応ということの中では、例えば、一方の手に持った対象を移動させるべき場所を探す先取り的な役割を持った触覚として発展する可能性を持っているということが言える。
そして、また、運動を伴った能動的な触覚、例えばなぞるというような触覚による事物の形状や空間関係などの確認ということとの関連で言えば、そうした能動的な触覚は、たどるという到達的運動において途中に触れている手がかりそのものを確認するということ自体が目的となるということの発展として、考えていくことができるのである。
(イ)到達的運動に伴う触覚によってとらえれる空間的関係
到達的運動においては、あくまで目的は終点の対象への到達であって、触覚的な受容自体はその目的ではないが、たどるということの中で一定の触覚的な外界の空間的な把握というものは存在しており、運動の高次化に伴ってその把握も発展していくと考えられる。
具体的には、まず、線状の手がかりを1方向にたどっていく運動を通して手もとを中心として遠心的な1次元で1方向のある種の触覚的な空間的把握が生まれる。これは前稿までで繰り返し述べてきた手もとを中心として前方に延びる放射線状の方向であり、放射線的に延びていくそれぞれの方向を、相互に関係づけるものはまだないが、その中でも、垂直の棒のように空中に延びていく手がかりをたどるのではなく、机に代表される基底面の上の手がかりをたどるような運動においては、そうした放射線状の方向を基礎づける場としての平面が構成され始めたと言えるかもしれない。これは、また、奥行きということから考えるならば、隔たった対象へ向かって手を伸ばす中に感じられている奥行きの実感を、面上の関係として置き換えることにつながるものと言える。
そして、さらに、線状の手がかりを選択を伴いながらたどっていく運動を通して左右に代表されるような相互方向的な1次元のある種の触覚的な空間把握が生まれる。そして、ここで、さらに面状の手がかりをたどることを通して、遠心的な方向と左右の方向が組み合わさったもっとも原初的な2次元のある種の触覚的な空間把握が生まれると言える。
ただし、ある種のというあいまいな限定を加えておいたが、こうした触覚的な受容は、到達という目的のための手段として起こっているのであって、触覚的な受容そのものが目的というのではない。したがって、過程自体が対象化されてまとまりをもった全体的な空間的関係としてとらえれるわけではないと思われる。触覚的に対象化される場合には、たえず全体が問題とされるので、往復的な運動を繰り返しながらいくつかの拠点の関係をまとめながら受容するような運動が必要であると考えられるのである。
そして、こうした能動的な触覚による確かめによって全体的な空間的関係の把握が起こるようになれば、それは、もう一方の運動を空間的に先取りしうるような働きを備えてくると言えるのであう。
2.対象の操作における終点の状態の確認と終点の先取り
ここでは、これまでの論稿で問題にしてきた運動として、面上をすべらせて終点に達する操作的な運動を中心に検討することにする。なお、冒頭で述べた通り、取得的運動もここに含めることになるが、水平に置かれた溝から抜き取るという運動は、このすべらせる運動とほぼ同様であるが、垂直の棒から抜き取るというような場合でも、棒に沿ってすべらせるということにおいて同じものとして扱うことにする。
(1)操作的運動と視覚
(ア)視覚による終点の状態の確認と先取りの出現
ここでは、すべらせる運動として、前稿で述べたスライド式のまるのはめ板とスライディングブロックとをその典型的なものとして、考察を進めることにする。
まず、視覚によって終点の状態を確認する場合について見ると、視覚の場合は、感覚と運動が同調する段階においては、手の運動や手が操作している対象を、運動の遂行にぴったり寄り添うように同調的に見るということが起こるが、そこから、次のような終点の状態の確認というものが生まれてくると考えられる。すなわち、運動がいったん終了したということが触運動感覚を通して受容された時、その終点において、手や手が操作している対象だけでなく、終点にある対象(スライド式のはめ板ならば穴、スライディングブロックならば終点のスイッチ)をも見る可能性が生まれ、両方を同時に見るということが起こると考えられるのである。こうした終点の状態は、初めは運動が終点で静止した状態における両者の受容から始まるものかもしれないが、しだいにそこには終点の直前から二つのものが接近して接触するところの確認に広がっていくと考えてよいだろう。ただし、それは、まだはっきりとした継時的な見比べというよりも、同時的な確認であろう。
ところで、これまで述べてきた運動には、往復運動が可能で終点に達する前の地点に戻ることのできる運動と、1方向性の運動のために終点からもとに戻るごとのできない運動とがある。そして、この両者それぞれに、終点の位置の先取りが生まれてくる可能性を考えることができる。
前者は、スライディングブロッタのように縁に沿って木片を滑らせていくような運動において起こりうるもので、終点のスイッチに到達した後、逆の方向の運動を起こして戻り、そこで折り返してもう一度スイッチを押すというような場合などであるが、こうした運動においては、終点の状態の確認は、単に終点の直前の状態から終点への1方向のみの変化の確認だけではなく、終点からもとの状態に戻る逆方向の変化の確認をも含むことになる。つまり、相互方向の、空聞的に可逆的な状態の変化の受容が起こる可能性が出てくるのである5そして、この空間的な往復運動を繰り返し受容することの中から、終点の位置の先取りという事態が生まれてくると考えられるのである。そして、こうした往復運動の反復の中で、空間的な先取りはより確かなものになる。なお、往復運動には、運動の起点まで戻るもの(図3A)と任意の折り返し点で再び終点に向かうもの(図3B)とが考えられる。
一方、1方向の運動からだけでも終点の状態の確認から、その運動を繰り返す(これは往復運動とは違い、一回ずつ区切られており、時間的な間もあく)うちに、終点を先取りする目の動きが生まれてくるということは、ありうるかもしれない。例えば、板をすべらせて入れるスライド式のはめ板の場合、いったん穴に入ってしまうと、改めてつかみ直して出すということはまた別の操作になるので往復運動は起こりにくく1方向の運動になりやすい。また、スライディングブロックの場合でも、必ずしも往復運動になるとは限らないわけである。だが、こうした運動においても、終点の状態の確認から、終点の直前から、手や手がつかんだ対象と、終点とを同時的に受容し、その変化をとらえることを行う中から、視線の移し換えを含んだ継時的な受容、すなわち終点の先取りというものが起こる可能性があるわけである。しかしながら、この場合も、終点の位置を先取りできるということは、手や手がつかんでいる対象を見て運動よりも先に視線を終点に移すことができるということであり、これは、終点に運動が到達した後、さらに視線を別の地点に移してそこへ向かって運動を起こすことができる可能性を持っているということを意味している。具体的には、縁の手がかりを減ら
したスライド式のはめ板で、はめた板を穴から.出して任意の地点に移動させることになる。そして、このことは、その地点から再び終点に向かって運動を起こすことができるということをも意味しており、これはすなわち、終点からその位置に向かう運動とそこから終点へ行く運動は往復運動になっていると言える(図4)。スライディングブロッタのように運動の方向が限定されている場合には、この別の地点は最初に起こした運動の経路上の点になり、そこかち再度終点への運動が起こる可能性があるわけだが、この別の地点への移動することの中にすでに往復運動が含まれることになる(結果的に図3Bと同じになる)。
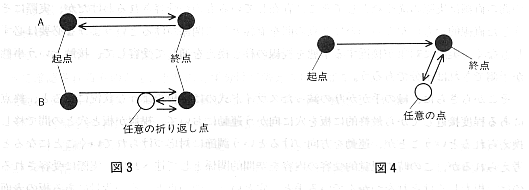 このように、終点の先取りができるようになると、往復運動が可能になり、実際に往復運動が起こったならば、前者の場合と同様になる。そして、やはり往復運動を通して位置の先取りは確かなものになると言えるのである。
このように、終点の先取りができるようになると、往復運動が可能になり、実際に往復運動が起こったならば、前者の場合と同様になる。そして、やはり往復運動を通して位置の先取りは確かなものになると言えるのである。
なお、こうした二つの可能性は、別の言い方をすれば、前者は、往復運動と感覚が同調する中から先取りが生まれてくるということで、往復運動の存在という運動の側の要因が先取りの必要条件となっているのに対して、後者の場合は、先取りが、1方向の運動との感覚の同調から運動の側の条件の特別な変化なしに生まれてきたことになって、先取りの出現の説明としては感覚の側の要因に重きを置いたものになっている。実際にはこの仮説の一方のみが成り立つのか、両方とも成り立ちうるのか、あるいは別の仮説を考えなければならないのか、その決め手となる事実には出会っていない。だが、どちらの仮説をとっても、先取りが確実なものになるためには、往復運動が重要な役割を果たすということは言えるだろう。
また、運動を起こす目的が、運動を達成するという最初の目的から、空間的な変化自体を受容するという目的へと変化するようになった場合、空問的な変化を繰り返し起こして反復的に確かめるということになり、この場合、往復運動が可能であるということは、不可欠の条件となると言ってよいだろう。
(イ)視覚による終点の先取りと空間的関係の受容
以上述べてきたようにして、視覚による終点の先取りというものが出現すると考えられるが、到達的運動においてもことわったように、先取り的に終点を見たということだけで、運動が調節される保証はない。視覚によって受容された内容が、それまで運動を調節してきた触運動感覚の内容と違うからである。先取り的に受容された視覚の内容が、具体的な運動の調節として対応づけられていくという過程が必要なのである。そこで、問題は、どのような視覚的受容の内容が、どのような運動の調節に対応するようになっていくのかということになる。
まず、スライディングブロックや両側に縁のついたIようなスライド式はめ板では、視覚的な受容がなくても十分操作の目的は達せられるわけだが、このような時の先取り的受容は、終点のスイッチや穴と操作している対象や手が接近していく状態というものが初めに受容されると考えられる(図5A)。そして、接近を告げる視覚的受容の内容は、運動を減速させるというような調節に対応づけられていくと考えられる。そして、この時の視覚的受容の内容を空間的関係として述べるならば、2点とその間が直線によってつながれ、その二つの対象が接近し接触するという動的な変化を含んだ関係であるということである。この場合、2点の間の直線は実際の溝や縁としてそこに存在しているものが受容されるわけだが、実際にそうした直線的なものがない場合に2点の問を直線として関係づけるというような必要は必ずしもなく、実際に対象が接近する事態を視線の移し換えを通して受容して、接触という事態が予灘できれば十分であろう。
そこからさらに、縁の手がかりの減ったスライド式のはめ板のような状況になると、終点にある程度接近してから最終的に板を穴に向かう運動において、視線が板と穴との閲で移し換えられるということが、運動を方向づけるという調節に対応づけられていくことになると考えられるが、この時の視覚的受容の内容を空間的関係として述べれば、実際に受容されるのは、板もしくはそれをつかんでいる手と、穴という二つの点と、その背景にある板の表面である。ところが、それだけでは二つの点は関係づけられたことにならない。そこに疸線でつながる関係が生まれなければならないのである。
それは、空中への到達のところでも述べたように、移し換えられる視線の動き自体が直線を描くということもあるかもしれないが、やはり、運動の軌跡の受容の中から構成されたものと考えた方がよいと思われる。そして、こうした二つの点とその間の直線の方向の受容が、運動の方向づけという調節に対応づけられるようになると考えられるのである。
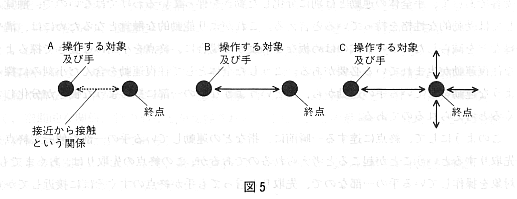 だが、こうした二つの点が直線によって結びつけられるという関係は、それだけでは、まだ図5Bのような1次元的なものにとどまる。ところが、実際にこうした運動は、方向づけだけであったら、方向がややずれたり、行き過ぎたりするということが起こりやすい。そこで、二つの点の受容は単に2点の間が直線によって関係づけられるだけではすまなくなる。すなわち、ずれたり行き過ぎたりした地点から、改めて穴に向かう運動の軌跡を受容することを通して、終点は、図5Cのような二つの次元の直線の交点として関係づけられるようになっていくと考えられるのである。そして、そのような関係が生まれた時、これはまさに2次元的なものと言うことができ、また、こうした二つの次元の結節点としての終点は、初めて位置と呼ぶに値するものとなるにいたるのである。ここで、背景としての板の表面は、方向や位置を規定する基底面(手もとの水平面)として構成されることになるのである。
だが、こうした二つの点が直線によって結びつけられるという関係は、それだけでは、まだ図5Bのような1次元的なものにとどまる。ところが、実際にこうした運動は、方向づけだけであったら、方向がややずれたり、行き過ぎたりするということが起こりやすい。そこで、二つの点の受容は単に2点の間が直線によって関係づけられるだけではすまなくなる。すなわち、ずれたり行き過ぎたりした地点から、改めて穴に向かう運動の軌跡を受容することを通して、終点は、図5Cのような二つの次元の直線の交点として関係づけられるようになっていくと考えられるのである。そして、そのような関係が生まれた時、これはまさに2次元的なものと言うことができ、また、こうした二つの次元の結節点としての終点は、初めて位置と呼ぶに値するものとなるにいたるのである。ここで、背景としての板の表面は、方向や位置を規定する基底面(手もとの水平面)として構成されることになるのである。
(2)操作的運動と触覚
触覚における終点の状態の確認は、操作的運動自体に伴う触運動感覚の中に未分化に含まれているところから分化した触覚によって確認されるものと、操作的運動とは別の触覚によって確認されるものとを、とりあえず分けて考えなければならない。すなわち、具体的には、運動している手自体の触覚と、運動していない方の手の触覚とである。
(ア)対象を操作する手と同一の手の触覚において
まず、運動を起こしている手の触覚について考えてみる。この場合、一方の手で分化した二つの役割を担うわけだが、運動の方は終了するため、運動の終了した後は純粋なかたちで終点の状態を確かめる感覚としての働きが前面に出てくることになるだろう。スライディングブロックの場合であればスイッチとの接触という状態が終点の状態であるし、またスライド式のはめ板の場合であれば板が穴に入るということが終点の状態になる。
そして、こうした終点の静的な状態は、さらに終点の直前の状態からの変化という動的な状態の受容が運動と一体化した触運動感覚の中から、浮かび上がってくると考えられる。しかし、このように同一の手で運動とそれを受容する触覚がかねられている場合、そのままでは感覚が運動に先行するということは起こりえないということになる。そこで、同一の手ではあっても、その手をさらに細かく分けた部分間で役割の分担ということが起こる可能性が出てくる。つまり、一個の対象物をつかんで運動を終点に向かって起こしている時、全体としてはまだ終点に達していないのに、終点の直前で手の一部が終点に触れるということが起こってくるのである。それは手のどこの部分でもいいとも言えるかもしれないが、手の働きが分化するのには、指という明確に分化した部分であれば、その役割の分化はよりはっきりとすることになる。
このように手の一部が終点の直前で終点に触れるというようなことは、終点の先取りというものを含んでいると言えるが、これは、運動の減速という調節に対して一定の役割を果たすと考えることができる。
そして、運動が溝や縁などによって1方向の直線運動になるような規制を受けている場合には、終点に達する直前に手の一部が触れると言っても、それは、運動の結果生じた触覚的受容であって、手全体の運動とは別に分化した動きを伴っているわけではないので、触覚としては受動的な性格を持っていると言える。これがより能動的な触覚となるためには、溝や縁などを減らしたスライド式のはめ板などのような場合に、終点を小刻みな動きで探るような往復運動が生まれている必要がある。こうした全体として往復運動を含んだ小刻みに探るような運動をしている手の運動から、指というような手の一部に探るような働きが分化してくると考えられるのである。
このようにして、終点に達する一瞬前に、指などの運動している手の一部を使って終点を先取りするということが起こると考えられるのであるが、この終点の先取りは、あくまでも、対象を操作している手の一部なので、先取りと、言っても手が終点のすぐそばに接近してからでないと、終点を先取りすることはできない。つまり、別の手がかりによって終点に接近してから、最後に終点に到達するための細かな調節に関して起こる終点の先取りなのである。しかし、こうした指などの手の一部が分化して、終点を探るような動きをするということは、そこに操作している対象と終点を結ぶ方向という空間的な関係を先取りするということが起こっているわけであり、たどる到達的運動のところで細かく見たように、二つの方向が組み合わさったような動きを伴うようになってくると、そこには、単に二つの点をつなぐ方向だけでなく、二つの次元の方向の交差する結節点としての位置という平面上の空間関係がとらえられ始めていると言えるのである。
こうした先取りがはっきりとしたかたちで見られるようになるのは、実際には、棒を穴にさすというような場合に、棒を握った手の薬指や小指などで穴を探してさすという運動などで、これはもう少し先の段階の議論となる。だが、こうしたはっきりとした先取りに先行するものとして考えておく必要があると思われたのである。
(イ)対象を操作する手と反対の手の触覚において
次にもう一方の手の触覚について考えると、ここでは終点の状態の受容を問題にするのだから、このもう一方の手は終点にある場合について考えることになる。それでは、このように終点で触覚としての手が運動してくる手を待っているという状態はどのようにしてもたらされたのだろうか。そもそも、終点に手があるという状態は、自発的に終点に到達するのでなければ自発的に起こることではない。そして、到達的運動のところで見たように、本稿の段階では、ある場所への到達そのものがいかにして可能かということを問題にしているので、ここでは、その触覚としての手が、自発的に終点へ到達するという状況が起こっていないところから考えていかなければならないのである。したがって、ここで終点にある触覚としての手は、私たちによって誘導されたものとして始まるということになるのである。
そして、この終点に置かれた手の触り方が、どのような水準にあるかということが問題になる。そこで、触覚の水準について簡単な区別をしておきたい。触覚は、その感覚の内容によって区別することが普通だが、触り方の水準という観点からは、触覚に伴う運動によって区別する必要があると思われる。そして、手のひらから指先にかけた触覚については、大ざっぱに次のように整理することができる。まず、もっとも受動的なものとして、全く運動を必要とせず、刺激が一方的に皮膚を刺激するというものをあげることができる。温冷や痛覚、圧覚、物の広がり、振動といったようなものはこうした状態でも受容できるものである。次に、ひっかく、たたく、握るというような瞬発的な運動を伴うものがある。これで、表面の材質感や硬さ、大きさ、つかみやすさなどが受容できる。さらに、持続的な調節を伴う直線運動や溝などの手がかり・に沿った運動、物の形状に沿った運動などを伴うものがある。これで、空間的な関係、物の形などが受容される。そして、この最後のものは、たどる到達運動と密接に関係したものである。
以上の区別をふまえた上で、終点で待っている手がどのように終点の状態を確認しているかということを考えてみることにしたい。
まず、最初にとらえられる終点の状態は、操作の対象あるいはそれをつかんでいる手が、終点で待っている手と接触するという状態である。この接触は、初めは、もう一方の手が運動してくることによって生まれるのであって、終点に置かれた手の方は、ほとんど運動はせず、受動的な性格を持った触覚であると言えるだろう。ただし、目に見える運動は見られなくとも、終点に手を置き続けられるということは、終点の付近をつかむなどの何らかの自発的な動きをもとにしており、そうしたことがバランスの調節に一定の役割を果たし、そのことを通して運動の調節に関与しているということは、忘れてはならない。
こうした終点の状態の受容は、運動の繰り返しの中で、さらに、運動が終点に到達する前の状態から到達した状態への変化の受容を含むようになると考えることができる。そして、運動が往復運動であれば、終点から再び離れていく状態の変化の受容もそこに含まれることになる。そして、こうした終点への到達の前後の変化として終点の状態がとらえられるようになるということは、すなわち、操作をしている手が接近することが予測されるようになっているということにほかならず、ここに終点の先取り的な受容が起こるということができる。この予測の手がかりは、その運動の持続時間であったり、視覚が利用される場合には視覚的なものであったりすることも,ありうるが、両手を体の前で合わせた状態に関する自己受容的な身体部位の位置感覚の果たす役割が大きいと思われる。このため、この先取り的受容は、触覚的な先取りというよりも、この自己受容性の位置感覚による先取りと言った方がよいかもしれない。
しかし、こうした身体の部位の位置関係の受容については、そのままでは、静的かつ固定的な身体部位の位置関係を意味するととられやすいが、この身体部位の位置というのは、運動している場合にはその運動に対応した一定の姿勢やバランスの中で、また、運動していない場合でもその時とっている姿勢とそのバランスの中で、その都度自己受容性の感覚を通してとらえられるもので、その運動あるいは姿勢やバランスと一体化したものであると考えられる。したがって、その時の姿勢やそのバランスが違えば、仮に同じ位置に身体部位があったとしても、受容の内容は異なってくると考えられるのである。しかも、こうした運動あるいは姿勢やバランスは、外界の状況と切り離すことのできないもので、その時の外界との関係に応じて違ってくるものである。したがって、こうした段階では、身体の位置関係というものは、ある外界の状況でそれに対応した姿勢を適切なバランスのもとでとりながら一つの運動を起こす時に、身体の各部分がどのような関係を持つかということを受容する中で構成されていくものであると考えられるのである。例えば、胸の前で両手を合わせるということと、ここで問題にしている机の上で両手を合わせるということは、一見、類似した位置関係にあるように見えるけれども、姿勢やそのバランスのとり方に大きな違いのある、異質な位置関係であり、後者の位置関係は、前者の位置関係を基礎としつつも、改めて新しい状況の中で、新しい姿勢やバランスを作りながら、構成し直すものだと考えられるのである。
こうした受動的な性格から始まった触覚に何らかの運動が起こって終点の状態を触って確かめるというところから少しずつ能動的なものになっていくと考えられる。そして、先に区別した触り方の水準で言えば、ひっかく、たたく、握るというような瞬発的な運動に対応する触り方が生まれてくるということになるが、ここでは、終点に置かれた手は終点から離れてしまうような大きな動きをすることはないので、指先で軽くひっかくような動きや手のひら全体で軽く押さえるというような動きを考えることができる。そして、実際に運動が起こる前にも誘導されてきた終点の状態をそうした動きによって触って確かめるということが起こりうるし、また、実際の運動が終点に到達した後にも、同じように終点の状態を確かめるというようなことが起こると考えられる。そして、これはさらに、終点の状態が、運動が起こる前と終わった後の二つの状態の違いとしてとらえられるようになっていくと考えられる。そして、運動が往復運動であれば、再び終点から離れていく状態も受容されることになる。ここでも、この待ち受けている手に先取り的な役割を見ることができるわけだが、ここで受容されているのは空間的な関係の変化というよりも触覚的な実感の変化なので、この触覚自体に空間的な先取りとしての意味はまだないと言えるだろう。したがって、ここでは上述した待っている手の位置感覚に基づく先取りということになる。
こうした触り方は、さらにその触り方に伴う運動が持続的な調節を伴ったものになってくると、いっそう発展することになる。すなわち、手のひらや指の運動を伴って、終点から離れてしまわない範囲で、表面の形状や輪郭に沿った運動などをするという触覚的な確かめというものが起こることを通して、操作している手や対象が終点にあるスイッチや穴などに接触したり入ったりしているという終点の静的な空間的な状態や、離れたところから接触してきたり入ってきたりし、さらには終点から離れていくというような変化を含んだ終点の空間的状態の確認というようなものが生まれてくると考えられるのである。そして、こうした終点の状態の確認が、終点付近での細かな運動の先取りとそれに基づく調節を可能にすると考えられるのである。
そして、たどる到達運動においてもふれたように、能動的な触覚としての働きを備えたもう一方の手が、終点に向かって自発的に伸ばされるようになれば、終点に到達するまでに触れた物と終点との空間的な関係といったような、机上という全体的な状況の中での終点の位置というものが確認されるようになると考えられるのである。具体的には、溝や縁といった操作対象の通り道の手がかりや教材の端などの他の部分、机の表面などに触れることによって、終点にあるスイッチや穴などの位置が確認されるということになる。そして、こうした終点の状態の確認は、外界の手がかりに基づく終点の先取りと、それに基づく運動の方向づけや位置づけといった調節を可能にすると考えられる。なお、こうした外界の手がかりに基づく先取りは、先に述べた両手を合わせるという身体の位置関係に基づく先取りとは区別されるもので、身体の位置関係に基づく先取りの上に、外界の手がかりに基づく先取りが重ね合わされるという関係にあると言えるだろう。
なお、こうした自発的な運動を伴った触覚的な確かめが顕著になってくるのは、二つの対象を空間的な隔たりを越えて関係づけるという運動、すなわちボ一ルなどを穴に入れるというような運動が成立し発展する途上においてであり、空間的な関係づけの始まりにおいて見られるのは、その萌芽的なものであると考えられる。
(ウ)触覚的役割と運動的役割の転換について
以上、対象を操作する手と終点で待ち受ける手というようにして、二つの手が異なる役割を分担しているものとして考察を進めてきた。確かにここで論じてきた段階においては、こうした役割は固定的なものとして進むことが多い。しかし、空間的な関係を先取り的に受容できる探るような運動というのは、単に終点で運動を待ち受けている受動的な触覚が単線的に発展してそのような触覚になるというわけではない。すでに述べたように、受動的な触覚の中から探るような運動を伴った能動的な触覚が生まれてくるのは、受動的触覚そのものが発展するというよりも、操作的運動である終点の付近での小刻みな往復運動から分化してくると考えた方がよいのである。また、さらに能動性の高い触覚として、自分から終点を探るような触覚についても、これは到達的運動のところで考察したように、たどるという到達的運動の発展として考えた方がよいのである。
このようなことを考慮すると、触覚の能動性の高まりは、運動や触覚という役割を固定化してはとらえきれないもので、一つの手の運動の中で、運動的側面が強くなったり、触覚的側面が強くなったり、あるいは両手の間で入れ換わったりするような中で発展していくものと考えていかなければならないだろう。
例えば、一方の手の運動の中で考えれば、すでに述べたことだが、スライド式はめ板で縁の手がかりの少ないようなものの場合で、操作的運動として働いている手において、終点の近くで穴を探るという触覚的側面が強まり、さらにそこから、指が穴を探るというような触覚的側面が分化するというようなものをあげることができるだろう。
また、運動する手と待つ手の関係では、同じく縁の手がかりの少ないスライド式のはめ板で考えれば、終点の直前で、それまで待っていた手が板をつかんで一緒に入れるというように、運動的側面が強まるということなどをあげることができる。
したがって、これ以降の触覚の問題を考える上では、一つの手の働きの中で、触覚的役割や運動的役割が分かちがたく結びついており、状況に応じて両者は柔軟にその重みづけを変えるものと考えていかなければならないということになるだろう。
ところで、こうした柔軟な運動的側面や触覚的側面の転換が可能になるのは、それだけ外界が、客観的な空間として構成されてきたことを意味している。これまでは、外界はそれぞれの運動や感覚に引きつけられて把握されており、それぞれに応じて違った外界が把握されていたと言えるような状況であったため、一つの運動の中では、それぞれの体の部分の運動や感覚の役割は固定的に進んだのである。しかし』ここにいたって、主体とは独立して存在する一つの外界というものが構成されてきつつあるため、その一つの外界に対して主体の方の複数の働きが、同一の外界というものとかかわるようになり、相互の調整を図りながら、柔軟に役割を転換させたりすることがでいるようになってきていると言えるのである。
おわりに
以上、本稿では、前稿で論じきれなかった終点の状態の確認から先取りの出現について、論じてきた。しかし、扱っている行動の範囲から言えば、前稿からほとんど先に進むことはできていない。これは、先取り的な受容ということについての、私自身の理解がまだまだ不十分なために、いったん足踏みをして深め直す必要が出てきたからである。そして、この先取りの問題は、なかなか出現の現場というのに立ち会うことがむずかしく、私たちが出会うのは多く、まだそのような受容を始めていない状況にある人か、あるいは、すでにそういう受容を始めるようになっている人であることも大きな理由である。そのため、その分だけ、本稿は、仮説的な考察が多くなってしまった。しかし、私にとっては、先取りがいかにして出現するかという問題を実践的に解決していく上で、様々な可能性を考えても考えたりないような問題である。
たくさんの重要な論点の周辺をぐるぐる回りながら、核心に到達しないままに粗削りな論稿にとどまっているのは残念でならないが、私にとっては、この先に進んでいくための踏み石のようなものである。もう少し、この私自身だけのための作業を、この紀要の場を借りて続けていくことにしたいと思う。
註.こうした到達運動に対する視覚の関与の道筋について、同様の観察がピアジェ(1978)にある。彼は、視覚と把握の協応に関して5つの時期を区別し、第4期では、手に入れたいと思う対象と手とを同時に見れば把握運動が起こるという段階であったのが、第5期になると、手の位置にかかわりなく見たものを手でつかむというふうに発展すると述べていた.しかし、これは、私がこの箇所で述べていることといささか矛盾してしまう。ここでは、対象の存在が視覚的に受容されれば、特に手を視覚的に受容しなくても到達運動が起こるというふうに述べた。それには、対象を視覚的にとらえることによって、それが手でつかむことのできる物であるという予測が生まれ、必ずしも手が視覚的にとらえられていなくても手の運動が起こるというようになる必要があるわけだが、その予測は、具体的には、視覚でとらえた物を持つ、あるいは持った物を見るというようなところから生まれてくるものと考えられる。しかし、確かに、自分の手の存在する場所については、何らかの感覚的な確かめが必要であるという事例には出会ったことがある。そして、その場合は、いったん手を体のある部分につけてから手を伸ばすというようなかたちで自分の手の存在の実感やその位置を確かめていた。その点では、ピアジェの観察にあるような、手が視野に入っている時にのみ手を伸ばすということと意味の上では類似しているとも言える。なぜなら、これもまた、手の存在やその位置の確認であるからだ。しかし、視野の中に入った時に手を伸ばすというのは、何らかのかたちで、対象と手の見比べを前提としていることになってしまうのである。私たちの出会っている障害の重い子どもたちは、こうした視覚による見比べが出現するのにかなりの時間を要したりすることから、見比べが早いうちに成立する健常児においては、対象のみの視覚的な受容から到達の可能性を予測して到達運動を起こすだけの豊富な経験を得る前に、見比べが未分化ながら成立していれば、対象と手を見て初めて到達の可能性に気づくというピアジェのような観察が生まれることになりうる。反対に、障害の重い子どもたちの場合、見比べが成立する以前に、視覚による対象の受容が対象への到達可能性を予示することがあるために、こうした事態が起こっていると考えられるのである。
参考文献
柴田保之 1993『対象物の空間的な関係づけへの道程』國學院大學教育学研究室紀要第28号
ピアジェ.J. 1978『知能の誕生』(谷村覚、浜田寿美男訳)ミネルヴァ書房
戻る