|
大宋の道圓三蔵と西域旅行 土肥義和 |
|
|
沙門道圓は、唐初期の三蔵法師玄奘没後300余年をへた、五代後晋朝から北宋朝初期の40数年間、前半は西域・インドへの求法僧(往西天取経僧)として、後半は国都開封かいふうの訳経院で梵語仏典の翻訳僧として活躍した高僧である. 彼の業績は、宋の第二代太宗皇帝の認められるところとなり、おそらく彼の生地であった滄州(今の河北省渤海湾近くにある滄州市)の地名を冠した“滄州三蔵”の法号が勅授された。この滄州は古くは、漢代以降に渤海郡が置かれた所であり、隋唐時代には、幽州(今の北京)と黄河を結ぶ主要な運河である永済河えいさいがの中間地に位置し、唐代では陸上交通の要所となるばかりでなく、渤海を利用する海運の中心地となって船舶の往来が甚だ盛んであった.玄宗皇帝は開元14年(726)に交通上、経済上の要地であるこの滄州に横海軍を置いてその保護に努め、貞元2年(786)以後になって、滄州は節度藩鎮の治所となり、五代・宋初へと引き継がれた。 |
|
|
道圓は後晋の天福年間(936-943)中、おそらく940年代の初めに中国を発って西域の諸都市を遊歴してインドに入り、6年間をついやして五印度(全インド)の聖地を巡礼した。彼は帰国の途中、西域南道沿いの最大の仏教王国である大宝于闐うてん国王(李聖天)治下の匝摩寺そうまじにおいて一般大衆への仏教教化活動の一環として、八関戒の戒牒かいちょう(八関戒という戒を授けたことを示す証明書)を一人一人個別に授けている。このことは敦煌で発見された戒牒(S6264)によって明かである。この牒は漢文で書かれているが、文字面の五か所に于闐文字を用いた方形の朱印が押されていることから、匝摩寺が漢人の受戒者(曹清浄)に発給したことがわかる。 |
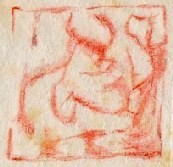 于闐文字の朱印 |
|
ここには天興12年(961)2月8日(悉達多シッダールタ王出家日)と于闐国の年号と日付が記され、最後の一行には、“授戒師・左街内殿・講経・談論・興教・法懐?大師・賜紫・沙門”の肩書(句点は筆者が便宜に付した)とそれに続けて道圓自身の署名がある。これによると、宋朝が創建された翌年の961年までには、彼は授戒師となり、かつ皇帝から法懐大師の師号を授けられた賜紫沙門であり、皇帝が国政をとる内殿において経論などの仏典を講義し、仏典の教化に勤める地位に抜擢されていたことになろう。 道圓は梵語サンスクリットのほか、于闐ホータン語にも通暁していたことは、彼が教学のために携帯していた「報恩経巻第四」の裏面に于闐文の仏教的テキストや医学文献を丁寧に写させている(P2893、熊本裕論文『講座敦煌6』参照)ことから窺える。道圓は于闐の朝貢使を伴い敦煌を経由して965年に開封に帰りついた。その歴程の20数年間は、玄奘三蔵の西域・インド旅行17年間をしのぐ驚異的なものであった。その間には後晋が亡び、つづく後漢・後周の二王朝も興亡して、宋朝建国後5年を経過していたのである。早速、宋の太祖の謁見を許された道圓は、インドから持ち帰った仏舎利の入った水晶器と梵経40夾のほか、旅行中に逐一書き留めていた西域諸国とインドの 諸情勢や各地域の地理・風俗・交通路などを記した、いわゆる西域旅行の調査記録を献上して太祖を驚喜させた。この記録は後世に伝わらなかったことが惜しまれるが、彼の報告が宋初の三代の皇帝の西域諸国招撫政策に影響を与えることになった。このことは道圓帰国後の翌年に僧行勤こうきんら157人が勅命によって西域諸国に派遣されたことや、965年から1005年の間に、大食カラハン国・天竺国・迦湿弥羅カシミール国・于闐国等の朝貢使節が頻繁に国都を訪れていることによっても窺知される(拙稿、『講座敦煌2』参照)。 ここで留意すべきは、道圓の巡歴は、宋朝初期の西域招撫策に貢献したばかりでなく、国家的な仏教奉讃事業に拍車をかけたことであろう。この運動は、唐初期から中期に長安仏教界を中心に玄奘三蔵・義浄三蔵・不空三蔵・新羅僧慧超えちょう(704-780すぎ)等によって行われた梵語仏典の収集とその漢訳事業を約180年後nの宋代になって再興しようとしたものである。982年に太宗が建造した訳経院において、新しく捜し求めた諸梵経を勅命によって「御製新訳経」として編纂するに当り、梵字の漢訳を担当したのはまさに道圓であった。この時期には彼は、滄州三蔵の法号が授けられ(『宋高僧伝』巻三)、訳経院にいる中国人僧の中では最高の地位にあったと思われる。このような仏教奉讃事業は日本にも刺激を与えたようで、東大寺の学僧奝然ちょうねん・嘉因らは983年―989年の間に開封を訪れ、太宗に謁して勅版大蔵経や新訳諸経が下賜されている。 以上に見た如く、大宋の道圓三蔵は西域求法及び訳経僧として、また西域巡遊の旅行記を録した僧という点において、大唐の玄奘三蔵と比するに値する人物と言えよう。 (國學院雑誌103編10号より転載、平成14年10月刊) |
|