満足と成果との関係 (in わかりやすいオートポイエーシス(自己生産))
組織の満足と成果との関係は、分析単位が個人の場合では無相関であるが、分析単位が組織の場合では正の相関関係、しかも満足が原因で成果が結果という因果関係にある。なお、組織成果(organizational performance)とは組織目標が達成されている程度のこと(小木曽(2007:4))で、組織の有効性のことである。また、組織への満足はBarnardの能率を操作的定義したものである。
1 Barnerd理論1)
Barnard(訳1968:85)は「組織が存続するためには、有効性または能率のいずれかが必要である」と有効性と能率との関係を定式化した。組織の有効性(effectiveness) を「最終目的を達成するために全体状況の下で選択された手段が適切である」(Barnard(訳1968:246))こと、すなわち、つぎに定義する能率を除く狭義の組織成果である。 組織の能率(efficiency)とは「組織活動を引き出すに十分なほど個人の動機を満足させて、組織活動の均衡を維持すること」(Barnard(訳1968:250))である。なお、Barnardのefficiency概念の定訳は能率となっているが、この能率は日常語や他の研究者の「能率」とはまったく意味が異なることに注意されたい。そして、この「組織の能率は組織成員の組織への満足と貢献意欲によって操作的定義することができよう」(小木曽(2007:103)。
2 ホーソン研究とその影響を受けた研究2)
ホーソン(Hawthorne)研究とは、Roethlisberger and Dickson(1939)によりその結果が公表された、Chicago近郊のWestern Electric社のHawthorne工場における1927年から1932年にかけての5年間に渡る実験および調査研究である。継電器組立試験室(relay assembly test room)実験は、どのような作業環境であれば成果3)が向上するのかを探索することを目的とした実験であり、実験の設計は、被験者は継電器の組立に従事する6名の女性従業員(うち5名は作業員、うち1名はレイアウト・オペレータ)、作業内容は電話機の部品である継電器の組立であった(Roethlisberger and Dickson(1939:19-31,60-2)参照)。実験の結果は、出来高給の導入、休憩時間の導入、就業時間の短縮によって、各週の1時間あたりの生産個数の平均(以下、「成果」と略す)は増加したが、しかし、休憩時間をなくし週48時間労働というもとの条件に戻しても、成果が向上する、いう神秘的な結果が判明した。
ホーソン研究の影響を受けて、満足と成果との関係についての調査研究が行われるようになった。個人を分析単位として満足と成果との関係を分析した研究においては、概して、満足は成果とは無相関であった。一方、満足と成果との関係を分析した研究の中には、Giese and Ruter(1949)やLawshe and Nagle(1953)のように、アグリゲートの技法を用いて組織や集団を分析単位としたものがあり、これらの研究では、満足と成果とは正の相関関係が認められる傾向があった。Brayfield and Crockett(1955:405)が指摘したように、満足などのモラールは集団の現象として成果と正の相関関係を示すものであり、分析単位を集団や組織とすることが妥当であろう。
3 期待理論 4)
1960年代以降においては、満足と成果との単純な相関分析はもはやほとんど行われなくなり、満足と成果とのどちらが原因でどちらが結果なのか、という因果関係の上での順序関係が新しい研究課題として取り上げられるようになった。満足と成果との因果関係については、まず、Lawler and Porter(1965)が、満足は成果の向上に伴う内在的・外在的報酬の増加と報酬配分の公正さの知覚によって引き起こされると仮定し、成果が原因で満足が結果であるという仮説を立てる期待理論を提唱した。
そこで、Wanous(1974)が80名の女子電話交換手を対象に3ヶ月の期間をおいた2時点のパネル・データをもとに、成果と満足(Weiss,et.al.(1967)のMSQ(Minnesota Satisfaction Questionnaire))との交差的時間差相関分析(【を開く】)を行った。その結果、
相関係数(γ)は、先の時点の成果と後の時点の職務満足(0.24)、外在的満足(0.19)、内在的満足(0.37)との交差的相関がもっとも強く、先の時点での成果と職務満足(0.09)、外在的満足(0.14)、内在的満足(0.10)との横断的相関、および、後の時点での成果と職務満足(0.15)、外在的満足(0.18)、内在的満足(0.15)との横断的相関が中間で、先の時点の職務満足(0.18)、外在的満足(0.30)、内在的満足(0.12)と後の時点の成果との交差的相関がもっとも弱い、という因果関係の要件を満たさず、成果が原因で満足が結果であるとは立証できなかった(図1)。さらに、これらの交差的相関および横断的相関は0.10~0.37とほぼ無相関であった。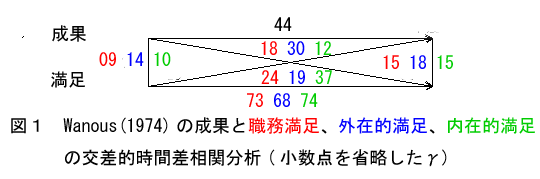
なお、このような満足と成果との関係は、個人を分析単位とするものであり、集団や組織を分析単位とした場合では異なる結果が得られることが考えられよう。
4 異なる分析単位での満足と成果との関係
分析単位が個人の場合における組織への満足度が高い組織成員の成果が高いことと、分析単位が組織の場合における成員の組織への満足度が高い組織の成果が高いこととを混同してはいけない。小木曽(2007:131)は、会社への満足(分析単位が組織の場合では会社への支持)5)と(組織の成果(有効性)を操作的定義した)相互評価による生産性6)との関係が、分析単位が個人の場合では0.16と無相関であったが、分析単位が組織の場合では0.40と正の相関関係にあったと報告した。
5 組織を分析単位とする場合の満足と成果との因果関係
正の相関関係が認められた、組織を分析単位とする場合の満足と成果との因果関係について、パネルデータを用いて交差的時間差相関分析を行った結果【を開く】、(会社への満足をアグリゲートした)会社への支持が原因で、相互評価による生産性が結果であるという因果関係が認められた。
| 1) | Barnerd理論については、小木曽(2007:3-6)を参照されたい。 |
| 2) | ホーソン研究については、小木曽(1997:56-8)および小木曽(2007:103-4)を、満足と成果との関係についての調査研究については、小木曽(1997:57-9,66-71)および小木曽(2007:126-9)を参照されたい。 |
| 3) | Roethlisberger and Dickson(1939)の"efficiency"は「能率」でも「有効性」でもなく、「成果」と訳出した。 |
| 4) | 期待理論については、小木曽(1997:68-9)を参照されたい。 |
| 5) | 会社への満足・支持については、出力例で用いたデータの出典と文献|SPSSの使い方【を開く】、小木曽(1997:155-9,271-2)、および、小木曽(2007:105-9)を参照されたい。 |
| 6) | 相互評価による生産性については、出力例で用いたデータの出典と文献|SPSSの使い方【を開く】、小木曽(1997:163-6,272-3)、および、小木曽(2007:118-9)を参照されたい。 |
§参考文献§
- Barnard,C.I.(1938) The Functions of Executive, Camblige, Mass.: Harvard University Press、バーナード著 山本安次郎・田杉競・飯野春樹訳(1968)『新訳 経営者の役割』ダイヤモンド社
- Brayfield,A.H. and Crockett,W.H.(1955) "Employee Attitudes and Employee Performance", Psychological Bulletin, 52:396-424
- Giese,W.J. and Ruter,H.W.(1949) "An Objective Analysis of Morale", Journal of Applied Psychology,33:421-427
- Lawler,E.E.Ⅲ. and Porter,L.W.(1965) "The Effect of Performance on Job Satisfaction", Industrial Relations,77:20-29
- Lawshe,C.H. and Nagle,B.F.(1953) "Productivity and Attitude Toward Supervisor", Journal of Applied Psychology,37:159-162
- 小木曽道夫(1987)「組織の構造の三次元と自己組織化過程」『組織科学』第21巻第3号、63-74頁
- 小木曽道夫(1997)『組織の自己革新~知識集約的部門の現場から【を開く】』夢窓庵
- 小木曽道夫(2007)『自己生産する組織~組織の環境、公式構造、課業特性、能率、および有効性の関係【を開く】』夢窓庵
- Roethlisberger,F.J. and Dickson,W.J.(1939) Management and the Worker, Boston, Mass.: Harvard University Press
- Smith,P.C., Kendall,L.M. and Hilin,C.L.(1969) The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement: A Strategy for Study of Attitudes, Chicago: Rand McNally
- Wanous,J.P.(1974) "A Causal-Correlational Analysis of the Job Satisfaction and Performance Relationship", Journal of Applied Psychology,59:139-144
- Weiss,D.J., Davis,R.V., England,G.W. and Lofquist,L.H.(1967) Manual for Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota: University of Minnesota