2023年度第5回日本文化研究所研究会開催のお知らせ
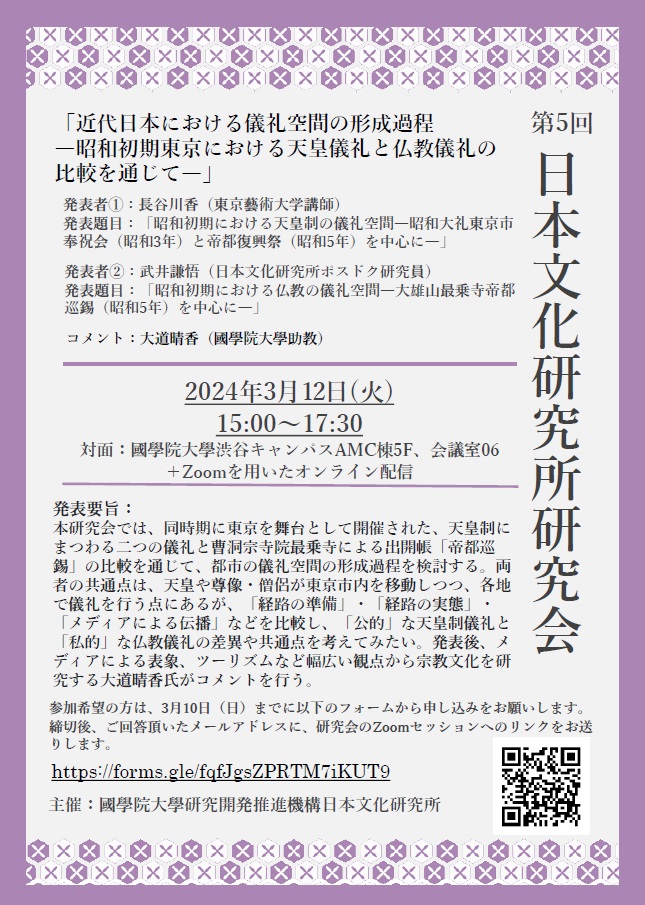
日本文化研究所は、3月12日に第5回日本文化研究所研究会「近代日本における儀礼空間の形成過程―昭和初期東京における天皇儀礼と仏教儀礼の比較を通じて―」を開催いたします。
[詳細]| 研究所について | アーカイブ | 刊行物 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所長挨拶 | 設立の趣旨 | 過去の催事 | 日本文化研究所紀要目次 | 刊行物一覧 |
| 事業概要 | 設立の経緯 | 図説による神道入門 | 日本文化研究所報目次 | |
| スタッフ紹介 | 双方向論文翻訳一覧 | 所蔵雑誌情報『禅』 |
![2023年度第5回日本文化研究所研究会[2024/3/12]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20235.jpg)
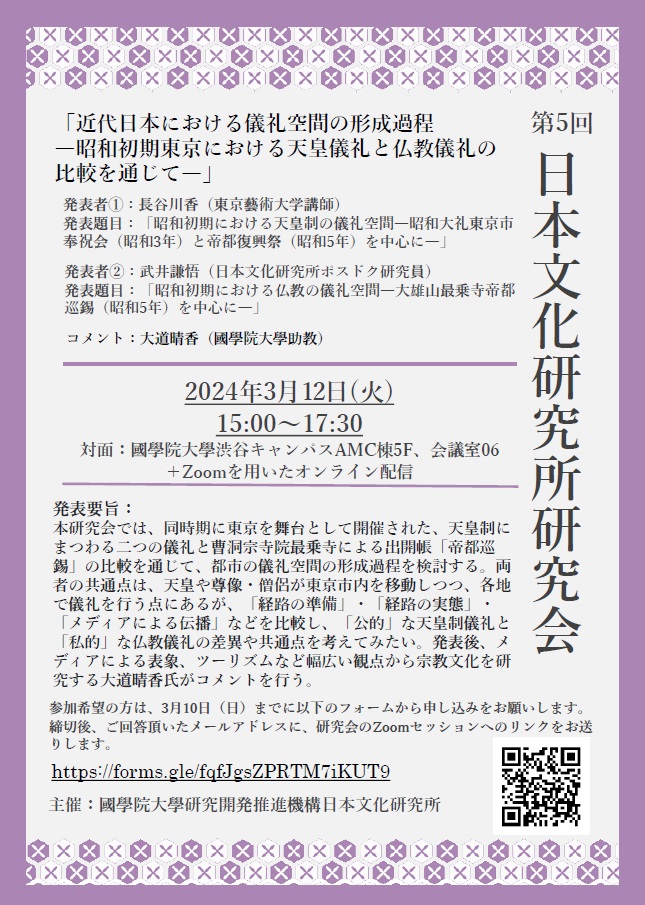
日本文化研究所は、3月12日に第5回日本文化研究所研究会「近代日本における儀礼空間の形成過程―昭和初期東京における天皇儀礼と仏教儀礼の比較を通じて―」を開催いたします。
[詳細]井上順孝・日本文化研究所前所長(國學院大學名誉教授、日本文化研究所客員教授)が、下記の通り令和5年度の文化庁長官表彰を受けることになりました。
[詳細]![令和5年度国際研究フォーラム「見られることで何が変わるのか―ツーリズムと宗教文化」[2023/12/17]](/oardijcc/img/pic/20231217.png)
令和5(2023)年度国際研究フォーラム「見られることで何が変わるのか―ツーリズムと宗教文化 To Be Seen: Changes Through Interaction Between Tourism and Religious Culture」

| 日時 | 2023年12月17日(日)13:00~17:30 |
|---|---|
| 会場 | 國學院大學渋谷キャンパス120周年記念2号館1階・2101教室 |
| 主催 | 國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 開催形式 | 対面 |
| 報告者・題目 | ケイレブ・カーター氏 Caleb CARTER(九州大学准教授) 「自分を取り戻す/山里を取り戻す―修験道とツーリズムの交錯」 |
| 石本東生氏 ISHIMOTO Tohsei(國學院大學教授) 「「ギリシャ」:神話とキリスト教の舞台そして観光-文化遺産を活かす共存-」 |
|
| 加藤久子氏 KATO Hisako(大和大学教授) 「共生の物語をつむぎなおす―ポーランドに出現した2.5次元のユダヤ人街―」 |
|
| 沈昭良氏 SHEN Chao-Liang(写真家、華梵大学教授) 「写真と社会風景―『STAGE』『Singers & Stages』『台湾綜芸団』を例に―」 |
|
| コメンテーター | 山中弘氏 YAMANAKA Hiroshi(筑波大学名誉教授、日本文化研究所客員教授) |
| 司会 | 平藤喜久子氏 HIRAFUJI Kikuko(國學院大學教授、日本文化研究所所長) |
宗教とツーリズムは、グローバル化とあいまって、より一層相互に密接に関わるようになり、宗教文化を資源としてツーリズムを振興しようとする試みは、もはや珍しいものではない。それでは、宗教とツーリズムの交錯によって、どのような変化が生じているのだろうか。
宗教は、それが行われる場において、物体としてのモノや、実践としてのコトを伴うため、そもそも「見られる」ものであることになるが、誰もがスマートフォンを用いて日常的に写真や動画を撮り、かつ即座に発信することが可能になったという現代的な状況において、そのように「見られる」宗教は、どのように変容するのか。あるいは何を見せているのか。他方、それを「見る」人々の側も、見ることを通して何らか変化しているだろうか。
これは、現代社会における宗教の問題であり、必ずしも日本の宗教文化に限定された話ではない。本フォーラムでは、様々な現場で調査・研究を行っている研究者に、宗教とツーリズムの多様な交錯のあり方について報告してもらい、議論を深めたい。
![2023年度第3回日本文化研究所研究会[2023/9/13]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20233.png)
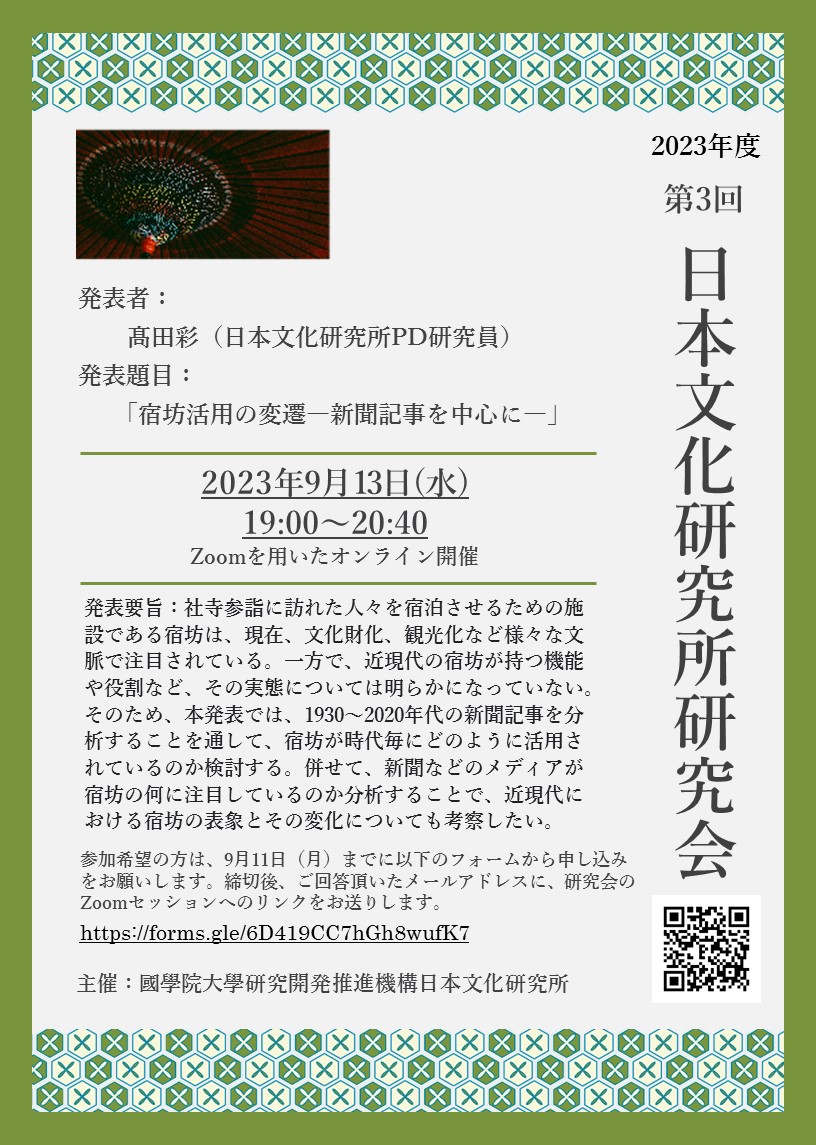
日本文化研究所は、9月13日に第3回日本文化研究所研究会を開催いたします。
日時: 9月13日(水)19:00~20:40
開催方式: Zoomを用いたオンライン開催
[詳細]![2023年度第2回日本文化研究所研究会[2023/7/3]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20232.jpg)
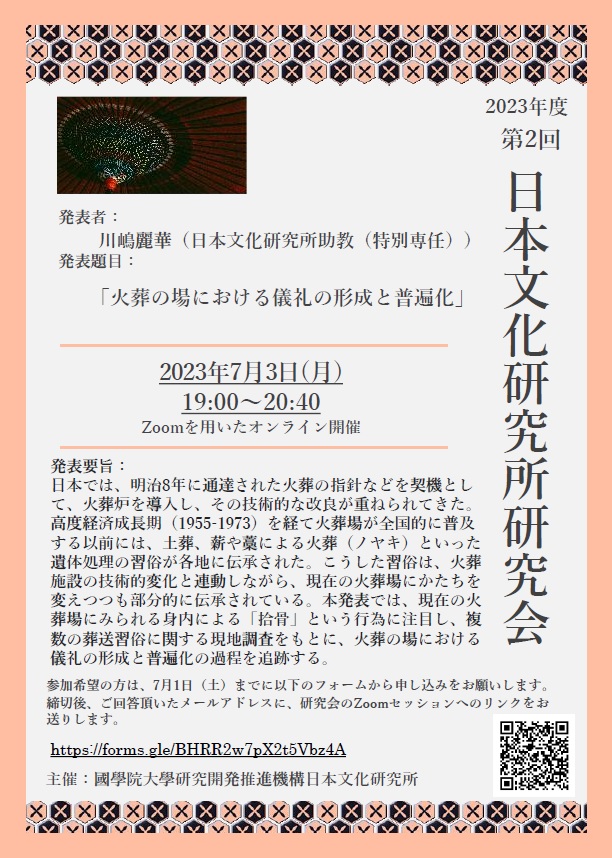
日本文化研究所は、7月3日に第2回日本文化研究所研究会を開催いたします。
日時: 7月3日(月)19:00~20:40
開催方式: Zoomを用いたオンライン開催
[詳細]![2023年度第1回日本文化研究所研究会[2023/6/28]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20231.jpg)
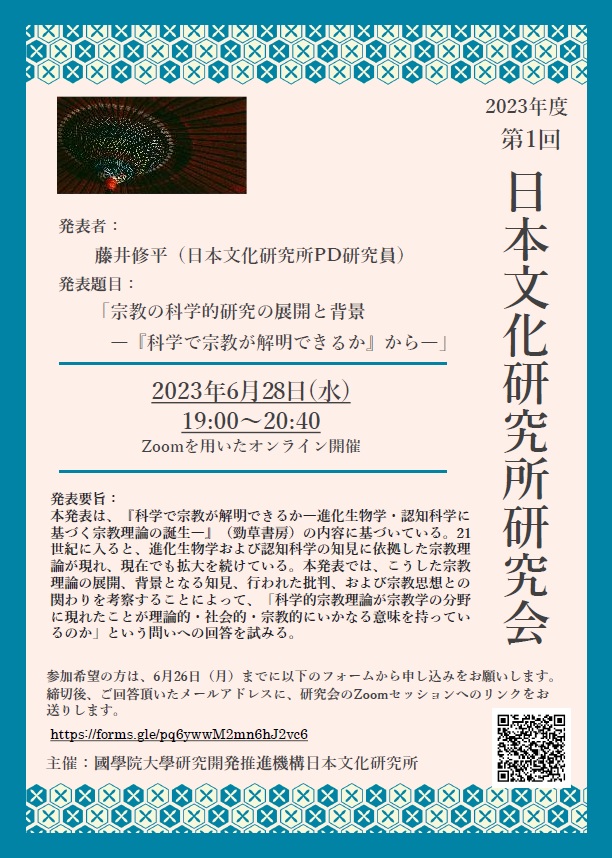
日本文化研究所は、6月28日に第1回日本文化研究所研究会を開催いたします。
日時: 6月28日(水)19:00~20:40
開催方式: Zoomを用いたオンライン開催
[詳細]![2022年度第9回日本文化研究所研究会[2023/3/28]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20229.jpg)
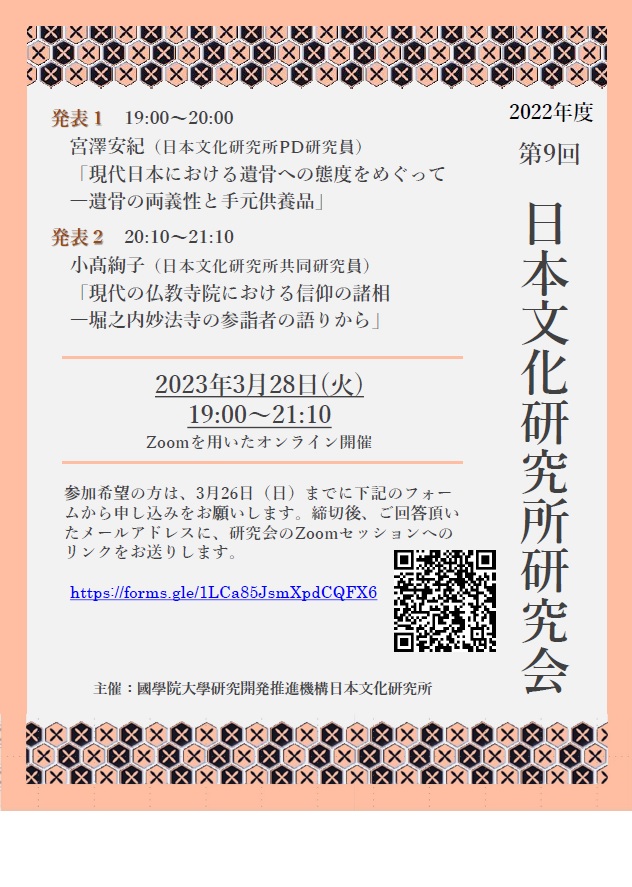
日本文化研究所は、3月28日に第9回日本文化研究所研究会を開催いたします。
日時: 3月28日(火)19:00~21:10
開催方式: Zoomを用いたオンライン開催
[詳細]![2022年度第8回日本文化研究所研究会[2023/3/7]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20228.jpg)
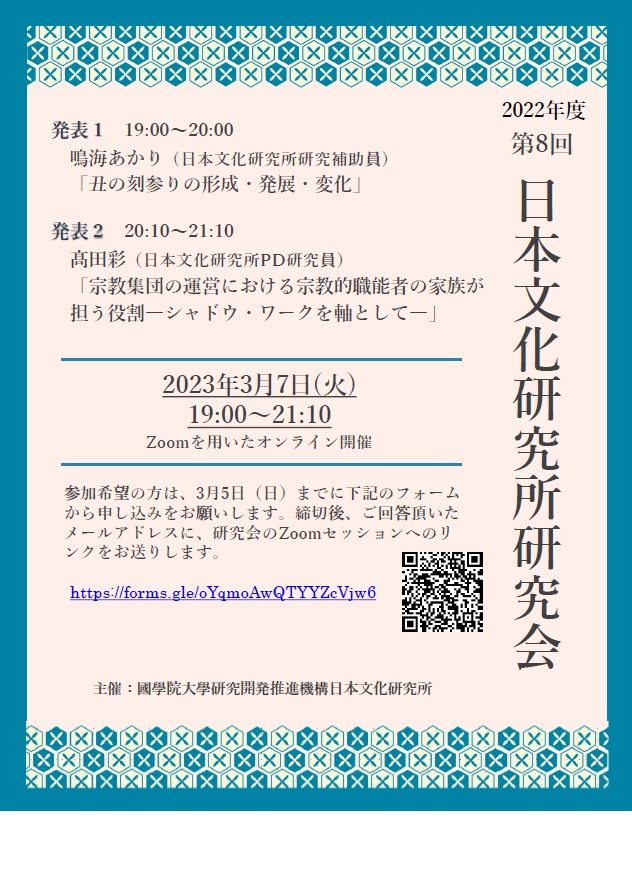
日本文化研究所は、3月7日に第8回日本文化研究所研究会を開催いたします。
日時: 3月7日(火)19:00~21:10
開催方式: Zoomを用いたオンライン開催
[詳細]日本文化研究所は、2月27日に学内研究会「島嶼部の伝統芸能をめぐる諸問題~三宅島にみたこれまでの活動とこれからの展望~」を開催いたします。本研究会では、三宅島において伝統芸能の調査・研究や啓蒙活動に努められてきた柳原友子氏にご発表いただきます。
[詳細]![2022年度第7回日本文化研究所研究会[2023/2/21]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20227.jpg)
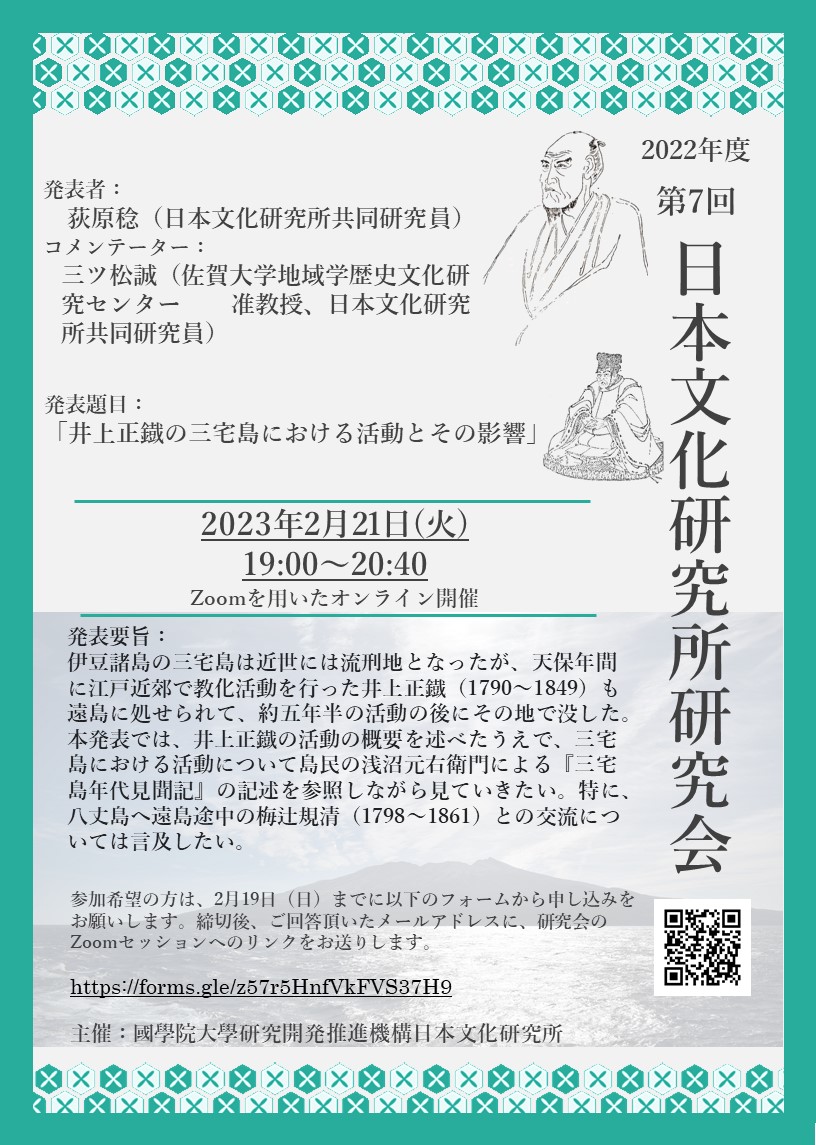
日本文化研究所は、2月21日に第7回日本文化研究所研究会を開催いたします。
日時: 2月21日(火)19:00~20:40
開催方式: Zoomを用いたオンライン開催
[詳細]