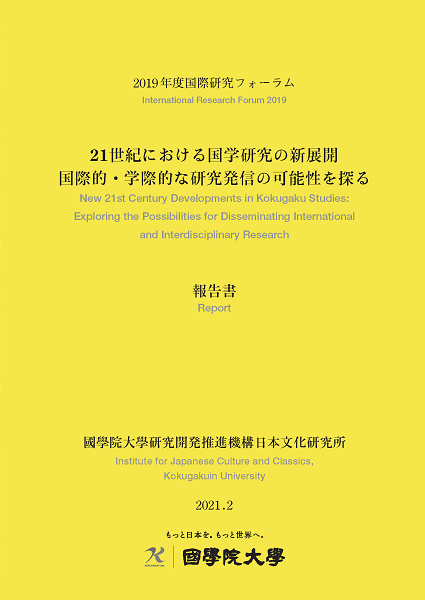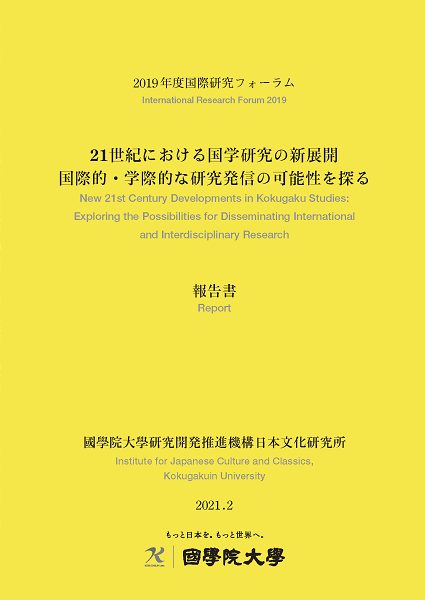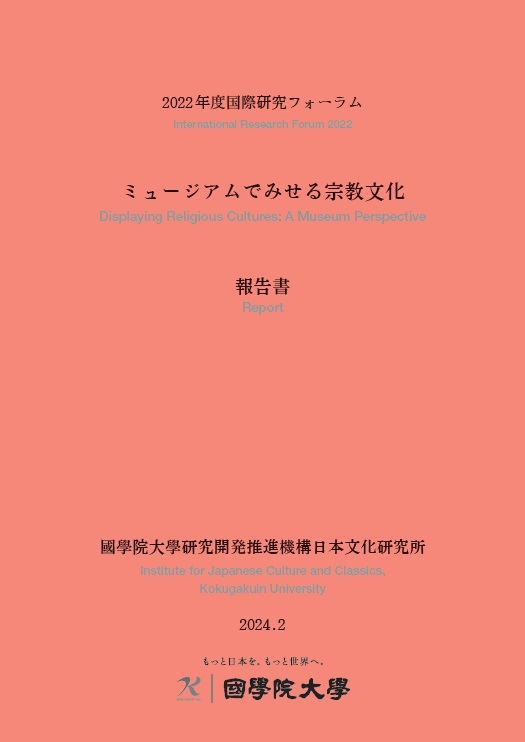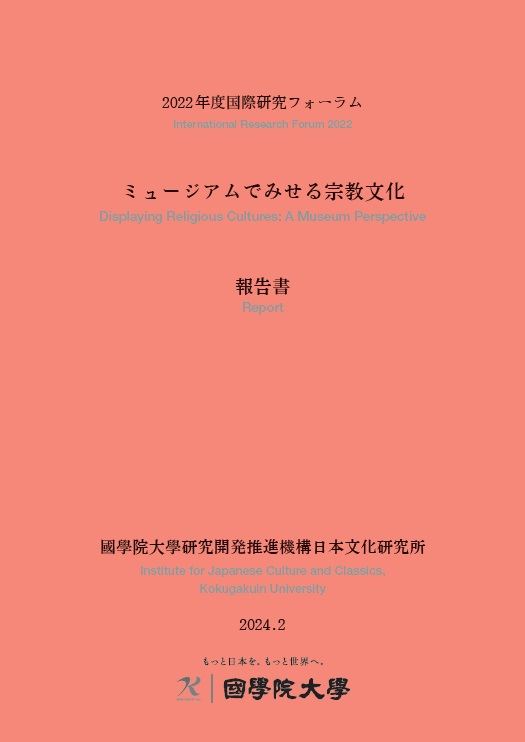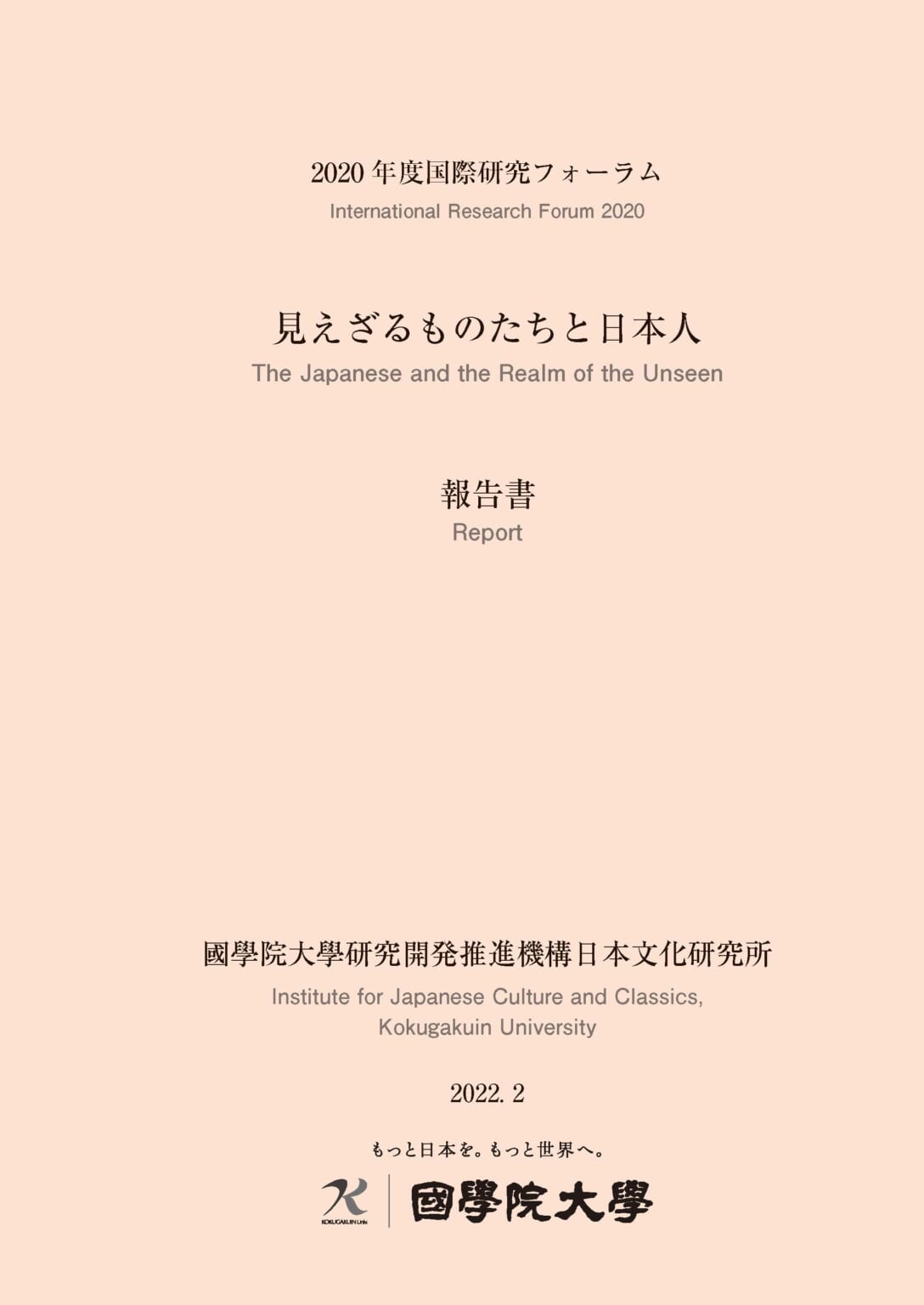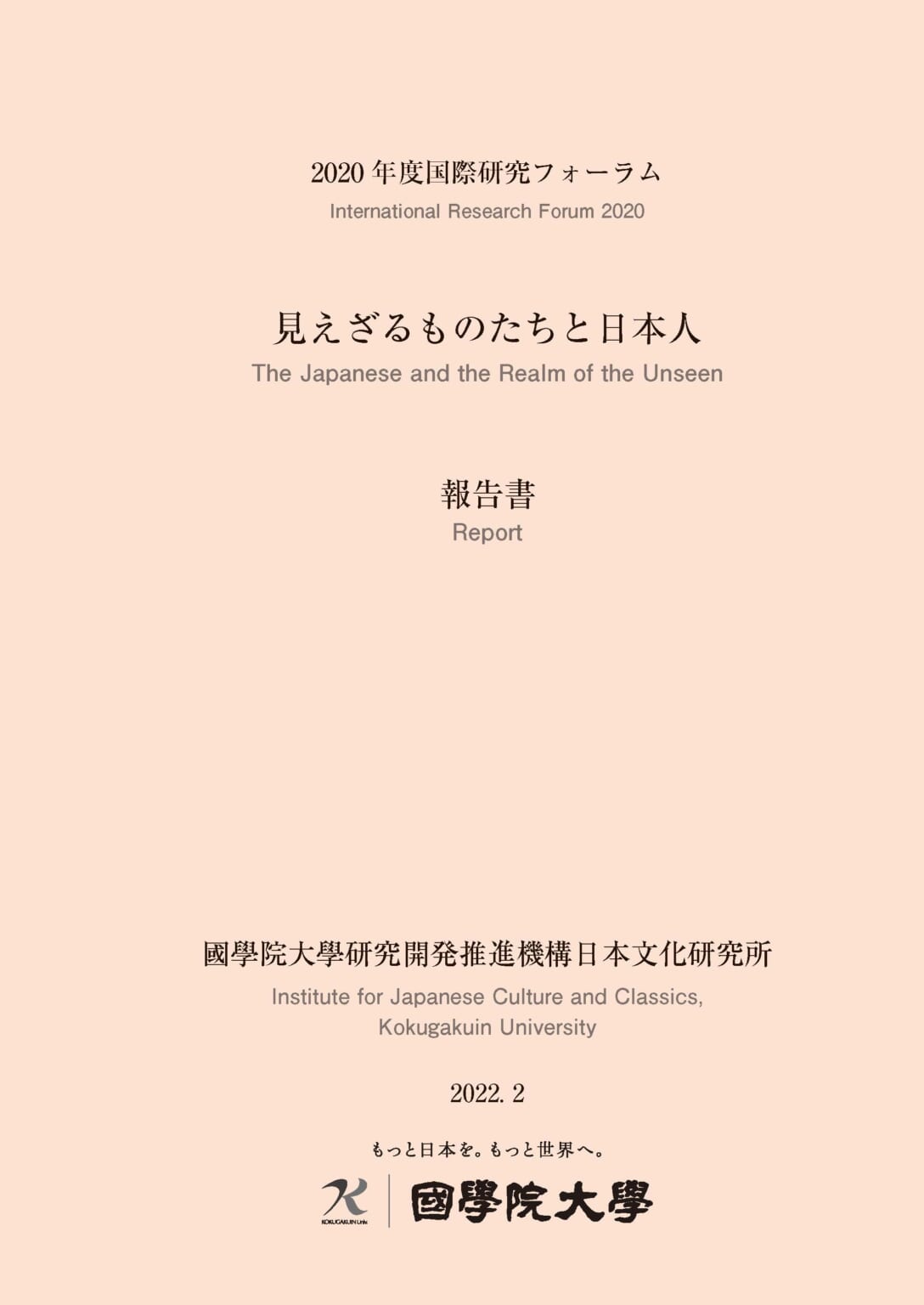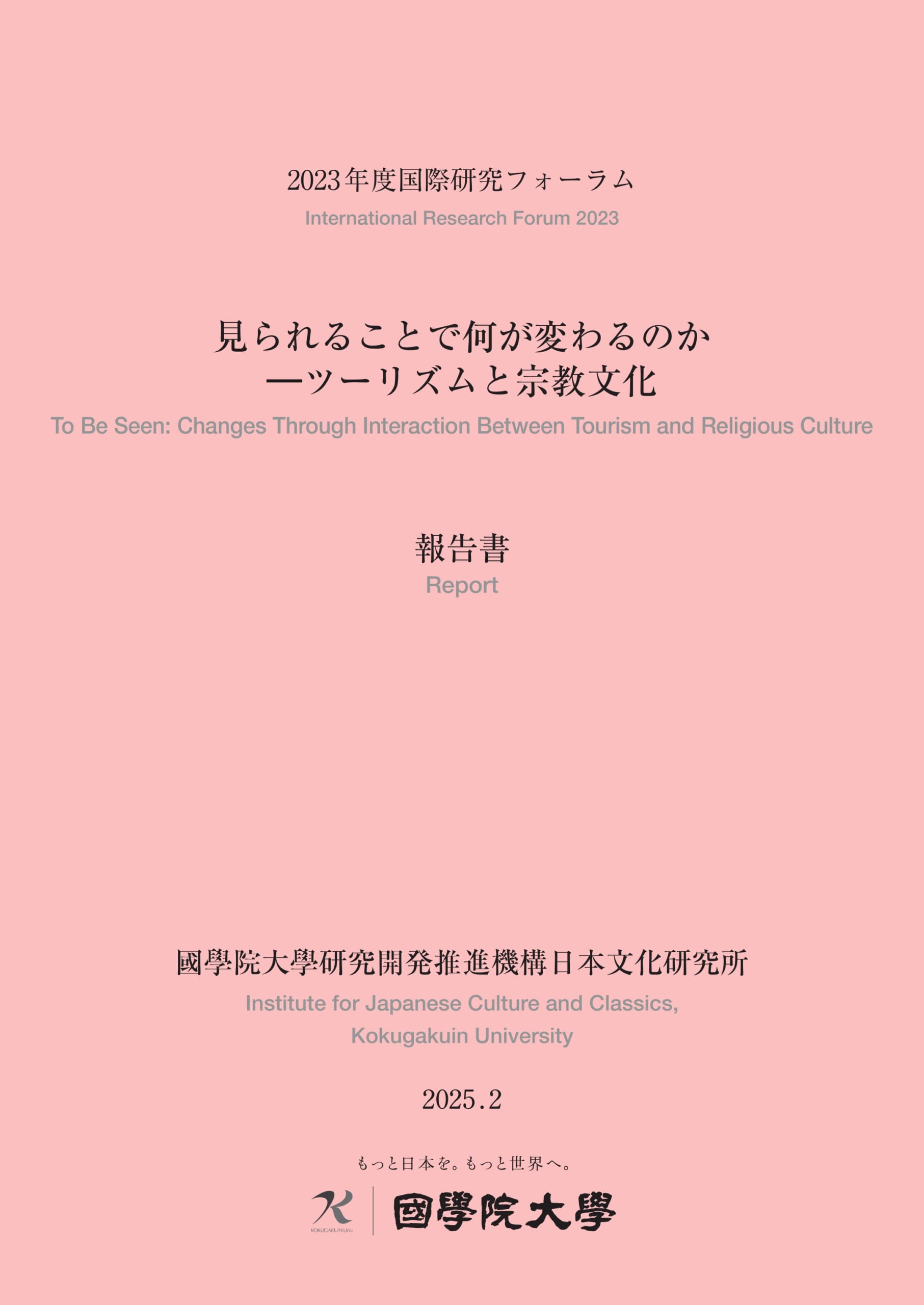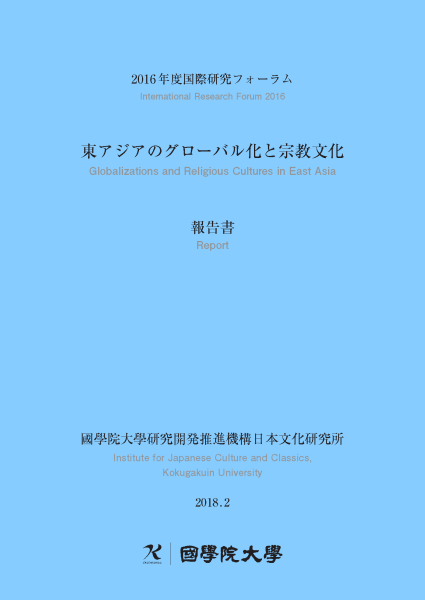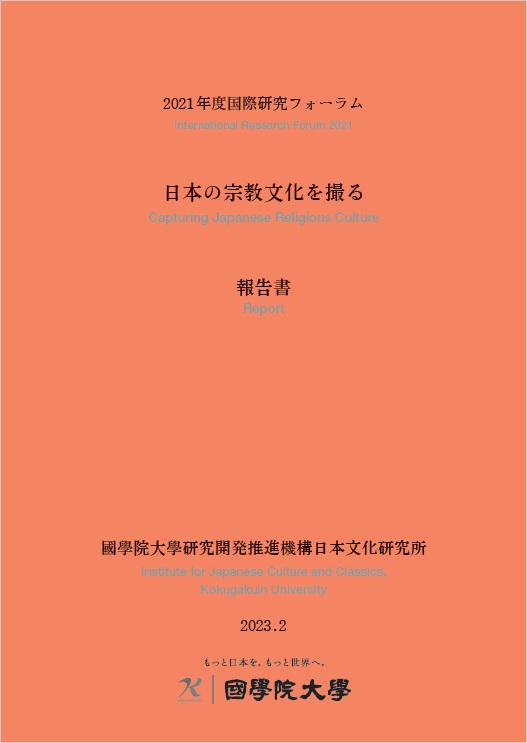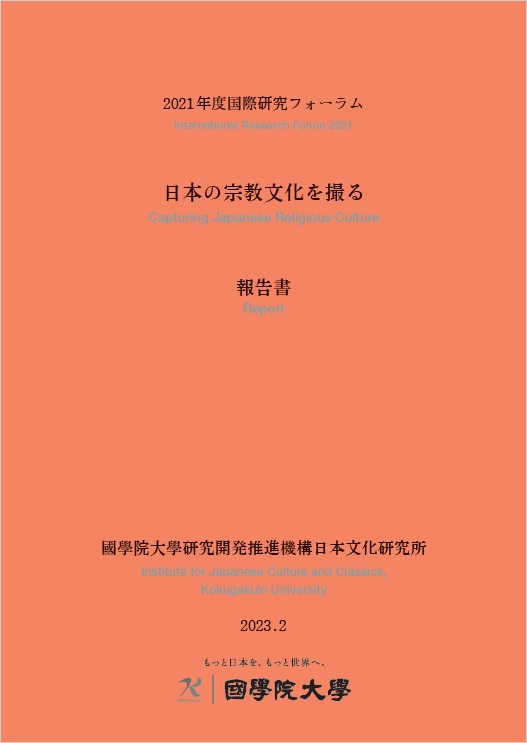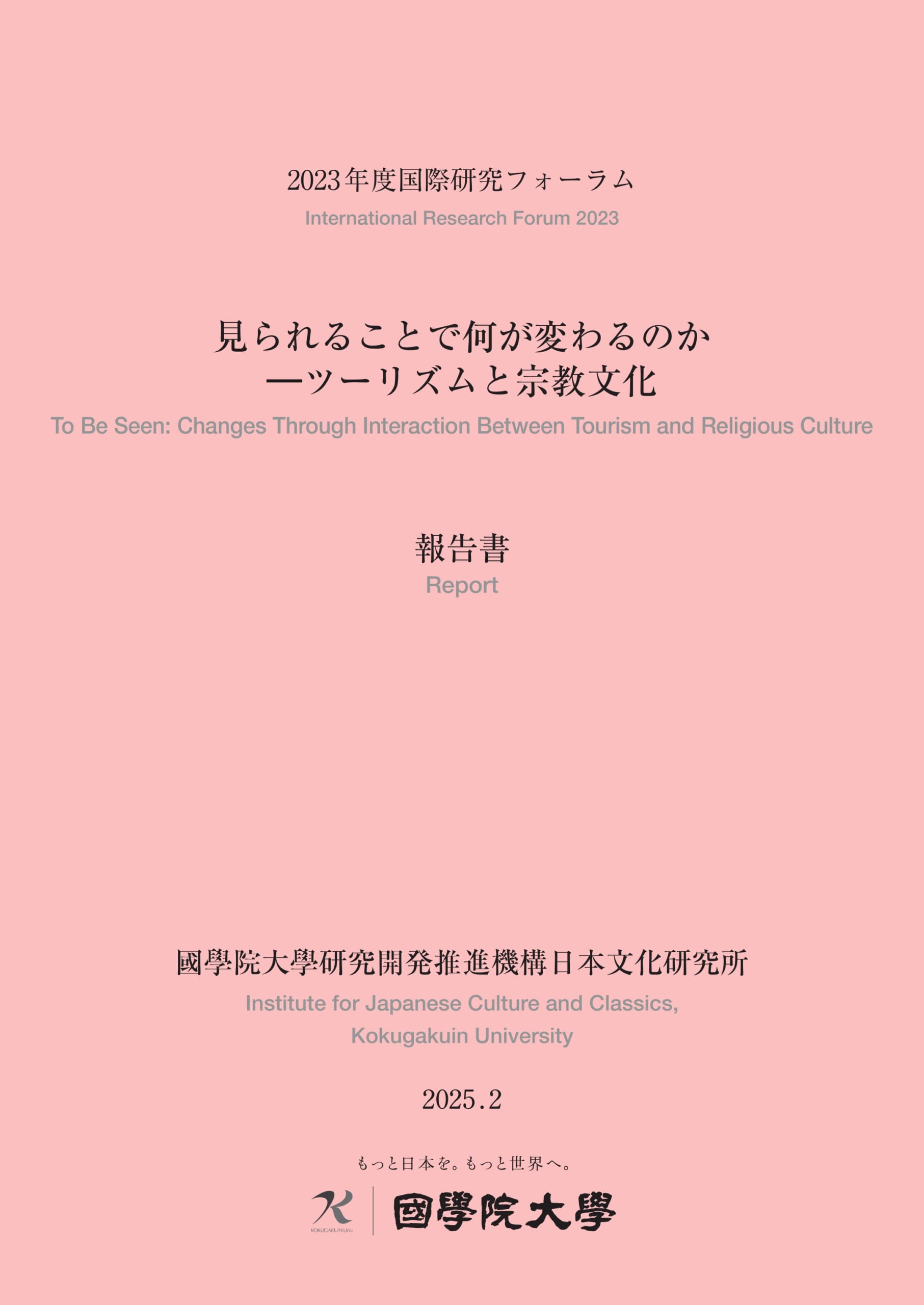
國學院大學日本文化研究所『国際研究フォーラム「見られることで何が変わるのか―ツーリズムと宗教文化」報告書』令和7(2025)年2月
本報告書は、2023 年12 月に國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所の主催で開催された国際研究フォーラム「見られることで何が変わるのか―ツーリズムと宗教文化」における議論をまとめたものである。
日本文化研究所は、設立当初より、日本の宗教文化について、国際比較の視点を組み込みながら、研究を行うことを一つの主要な目的としており、近年の国際研究フォーラムでは、特に視覚文化との関わりにおいて宗教文化を捉え直すことを試みてきている(「見えざるものたちと日本人」2020 年度、「日本の宗教文化を撮る」2021 年度、「ミュージアムで見せる宗教文化」2022 年度。なお、これらの報告書も日本文化研究所のウェブサイトで公開されている)。
これらのフォーラムでは、「見る」「撮る」「見せる」といった営みを念頭に置いて、そうした営みと宗教文化の関わりを問題としてきたが、本フォーラムは、これらを受けて「見られる」ということを論点として取り上げることとした。
では、現代において、宗教文化が「見られる」のはどのような局面であろうか。企画を議論する際に、前述の「見る」「撮る」「見せる」といった営みと一層密接に結びつくようになってきているツーリズムを主題とすることが提案され、ツーリズムと宗教文化が交錯する場において、往還的なまなざしを受けて、どのような相互変容が生じているのか――見られることで何が変わるのか――という本フォーラムのテーマが設定された。
コロナ禍を経て、今やツーリズムはあらためて隆盛しているように見える。そしてそれは、誰もがスマートフォンを用いて「見る」ものを写真や動画として「撮り」、それをウェブ上で不特定多数に対して「見せる」という現代的な状況と結びついているだろう。四つの報告は、それぞれギリシャ、台湾、ポーランド、修験道、と異なる事例を取り扱うものだが、いずれも、まなざしの問題に目を配りながら、ツーリズムと宗教文化の相互変容を取り上げるものである。本報告書が、現代における宗教文化のあり方を、あらためて考えるきっかけとなれば幸いである。(「はしがき」)
[詳細]